窓は心豊かな暮らしを創るポイント-3
2022/03/14

「窓」についての3回目。
住まう人の視点で考えた窓の6つのメリットの順を追って考えて行きます。
これまでの「採光」「通風」に続いて「眺望」について考えてみましょう。
眺望と言うと高層マンションの「もれなく東京の夜景がついて来る」などのキャッチコピーが頭に浮かびます。
眺望とは「広く遠くまで見晴らすこと」ととらえられていますが戸建住宅の窓からの「眺望」はロケーションにとっては「広く遠くまで見晴らすこと」も可能でしょうが多くの場合かなりの制限を受けます。
ここでは「眺望」を「窓からの眺め」と現実的に捉えて考えてみましょう。
「窓からの眺め」は住まいの必需品

「窓」のない部屋で長時間過ごすことは人間には耐えられません。
精神を病んでしまいます。窓は住まいの必需品です。
新幹線も飛行機も窓際の方が人気高いそうです。
もちろん日焼け防止で避ける人もいるでしょう、またエンターテイメント設備が装備された機内などでは長距離便では窓際との差は大きくないようですがやはり窓から離れた席からでも外の様子がうかがえることは必要なようです。
知覚の中でも「視覚」は人が情報を取得する最大の窓口で8割以上とも言われています。
もし「窓」からの眺めが得られないということになると不安な気持ちになってきます。
朝夕の感覚もなくなりますから体内時計も狂ってしまい心だけではなく体も病んでしまいます。
「窓からの眺め」は必ず必要です。
窓からの眺めを制御する

敷地の立地にもよりますが多くの住宅では「窓からの眺め」を全開放で眺めるわけには行かないというのが実情だと思います。
見たくない物も目に入るというのは嫌ですし、こちらから見えるということは向こう側からも見られているということにもなりますので観る側、観られる側のプライバシーも大きな問題です。
せっかく窓があるのにカーテンをいつも閉め切っているというのでは楽しくありません。
そのために「窓からの眺めを制御」する必要があります。
京都などの古くから人家が密集するエリアでは様々な「制御技術」を駆使して「窓からの眺め」を楽しんでいます。
「借景」という伝統的な手法の「大技」

京都の名刹などでは植栽や外構によって下部の視界を抑えて上方、つまり遠方に視点を集中させて遠景を「借りて来て」眺めるという「借景」という眺めを成立させる伝統的な制御技術があります。
京都中心部から東山三十六峰を借景にして「眺望」を得ているという名園は数多く知られています。
この借景の技術も敷地の条件に依りますが上手く使えるなら使いたい技術です。
「囲い庭」というプライベートな眺め

外部からの視線を外構などによって完全に遮ってプライベート空間を創りそこを眺めるという「囲い庭」の手法は敷地に制約がある中でも実現可能な手法です。
「窓からの眺め」だけでなく「囲い庭」は屋外空間を室内空間に引き込むなど心豊かな空間づくりも実現できます。
「囲い庭」を眺める窓は思いっきり開放的にしてもプライバシーを確保できます。
視線は「抜け」と「止め」がポイント

「借景」は遠景への視線の「抜け」ですが実は視界の下部を外構や植栽で視線を「止め」て制限しています。
「囲い庭」は視線を塀などを設置して敷地境界で視線を「止め」ますが塀の上方は空へ向けて無限大の「抜け」を創っています。
住宅街などの敷地条件ではこの視線の「抜け」と「止め」の考え方を応用することで「眺めを制御」します。
「眺めの制御」の事例
左の画像は室内側のFIX窓からの庭の眺めです。
室内外の一体感があり竹林風の風情のある眺めを演出しています。
右の画像の飛び石のあるところから手前が左の画像の庭になるのですがご覧の通り隣家は迫っています。
これが気にならないのは左の画像のように左右を障子で視界を制限し、上部は簾で視界を幾分抑えながら隣家の外壁をカモフラージュしています。
外壁の手前の植栽も含めて砂利、横に伸びた細長い池、その両側の竹なども相まって風情のある和風の良い眺めを生み出しています。
「窓からの眺めの上手な制御」です。


窓からの眺めを諦めない設計の工夫


「敷地が狭いから」「隣家が迫っているから」とあきらめずに工夫を凝らせば「窓からの眺め」は確保可能です。
お客様のパートナーである設計者が諦めない設計の工夫をすれば良い「窓からの眺め」を実現できますが、一方でコストは掛かります。
ここで過ごす時間の長さを分母にかかるコストを分子において時間当たりのコストを得られるメリットと勘案してご自身で判断してください。
「坪単価」発想から「心豊かな時間単価」発想へと切り替えて暮らし視点で判断してください。
まとめ
「窓からの眺め」は心身の健康を保ちより豊かな時間を生み出すために必要です。
そのためには様々な工夫が必要になりますがコストもかかります。
ただし得られるメリットは大きくしかも生涯に亘る長期間の心豊かな時間を手にすることができます。
設計者に様々な工夫を検討してもらってよく考えて判断しましょう。
《執筆者》
一般社団法人 住宅研究所
代表 松尾俊朗
一級建築士

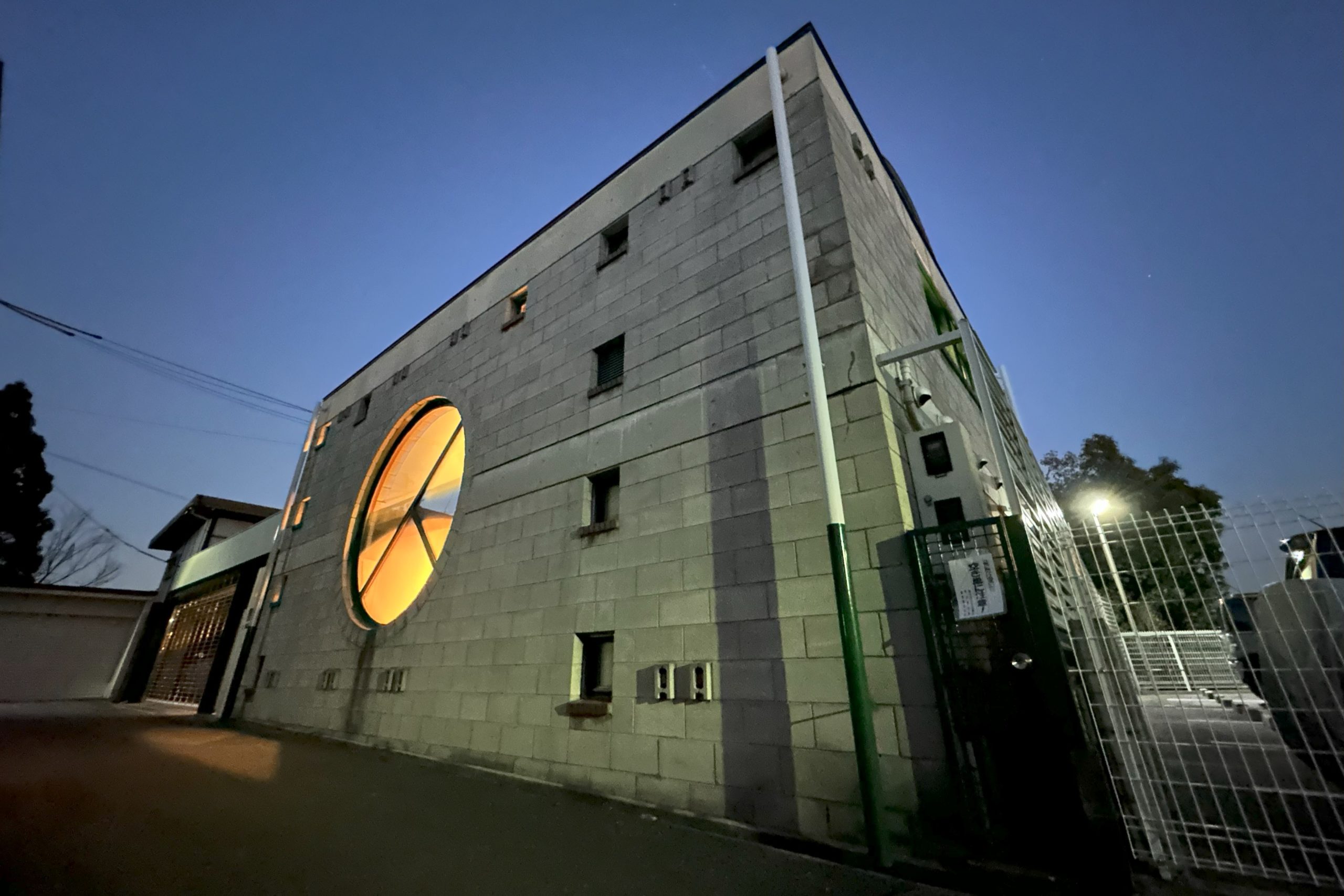


.png)





