モデルハウス・住宅見学会への「集客数の減少」をお客様の視点から見てみると
2024/04/26

モデルハウスや住宅見学会で、「集客が伸びない」「来場者数が減った」という声は、コロナ禍に突入してから多少の波はありますが常態化しています。また、人口減少や物価高などの社会情勢の影響もあり集客数は減少していますが、いずれにしても、住宅業界側からの集客数の減少の理由です。集客数減少の原因を、お客様側から見るとどうなのでしょうか。「集客数の減少」をお客様側からの視点も含めて多角的に考えてみましょう。
Contents
住まいづくりを思い立った人々の、モデルハウス・住宅見学会への行動様式が変化

総合住宅展示場来場者は場所にもよるでしょうが、従来は1度の来場時に3~4軒(平均3.4軒)程度のモデル住宅を観て回っていましたが、最近では1~2軒(平均1.3軒)程度のモデルハウスしか観ていません。これは、コロナ禍で多くの人との接触を避けて感染リスクを抑えるという行動様式が、住まいづくりの初期の行動にも影響を与え、定着した結果です。ということは、事前に住宅会社をネット検索で絞って、ほぼ狙い撃ちで来場されているということです。
「住宅建築適齢期」は「デジタルネイティブ世代」

1980年以降に生まれた世代を「デジタルネイティブ世代」と言われますから、ちょうど「住宅建築適齢期」の主力世代がこの層に当たります。
この世代の特徴は、「現実の出会いとネットでの出会いを区別しない」、「相手の年齢や所属、肩書にこだわらない」、「情報は無料と考える」、「オリジナルとコピーの区分の消滅」、「インターネットミーム(ネットを介して人から人へ模倣として拡がっていく行動)拡散力(SNSなどへの書き込みで拡散)」などがあげられます。
ネット検索とネットの口コミで候補に挙がった住宅会社/工務店のホームページを見て、「現実の出会いとネットの出会いを区別せずにこの会社がいいかな」としてモデルハウスや住宅見学会に来場されるという思考が行動結果に表れています。
●ベテラン住宅営業の自慢話は通用しない
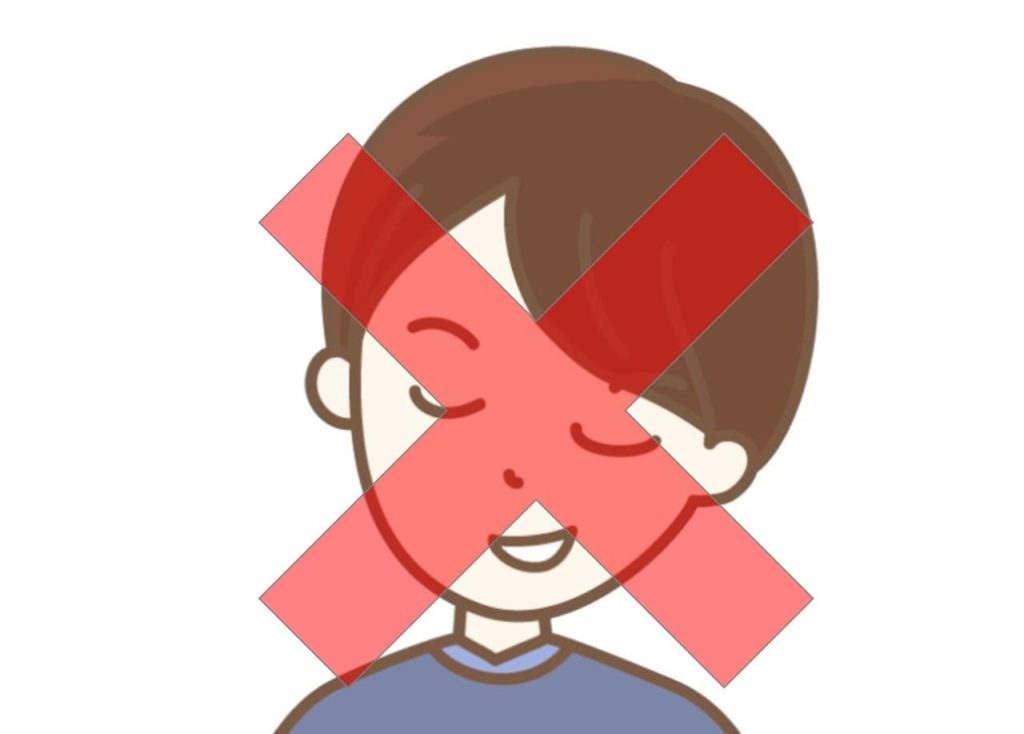
「相手の年齢や所属、肩書にこだわらない」ので「10年で150棟の受注実績」とか「3年連続受注コンテストゴールド賞受賞」とか、「住宅営業専任部長」とかの肩書を名刺に所狭しと記載している住宅会社を見かけますが、意味をなさず「自身の住まいづくりに役立つ情報を無料で提供してくれる住宅営業は良い住宅営業」となっています。
このことは、ベテランが通用しない現実と「新人だから役に立たないと思い込んでいる会社の固定概念」が破綻してしまっていることを示唆しています。
会社が伝えたいことを伝えるのではなく、目の前の固有名詞のお客様が求めている情報を理解して受容れて、適確に提供できるのかがポイントです。
これらのことは教育で対応できるということを示しています。
新人住宅営業は、経験が不足しているかもしれませんが、お客様も住まいづくりの新人です。
●「自社オリジナル」も通用しない

「情報は無料」で「オリジナルとコピーの区分が消滅」していますから、「自社独自の〇△□工法」や「オリジナルキッチン」などは、お客様が住宅会社/工務店を選択する理由にはならず、「情報として受け取っている」というのがお客様視点です。同じようなモノなら安い方を選んだ方が得、というようなネットオークション的な感覚です。
●「口コミ」は「画像コミと動画コミ」へ

「インターネットミーム(ネットを介して人から人へ模倣として拡がっていく行動)拡散力」を利用して自分の気に入った情報を手に入れておられます。
特に、Instagramなどの画像や動画で発信するSNSは分かりやすくインパクトがありますから、こうした画像や動画を持参されるお客様が当たり前化しています。
従来のモデルハウス・住宅見学会の見せ方、集客の仕方、接客応対の仕方を変える

冒頭の話しに戻って考えると、ご来場いただくためには、事前にネット上で選ばれる必要がありますので、ホームページやSNSでの情報発信を強化します。
耐震性や外皮性能、全館空調などの「モノの説明だけでは情報ではなく」、それらの「モノがもたらすお客様の暮らしの変化やメリットを情報として発信」します。
その際には、必ずビジュアルな画像、動画も使って伝わる情報とすることがポイントです。
モデルハウスや住宅見学会を見に来ていただくのも、「家というモノを見てください」というのは、昭和/平成時代の住宅の見せ方です。
令和の時代は、住宅の内容も「○LDKプランにあてはめて、こんな工夫もあるよ、程度の一般解の住宅」では通用しません。
「この住宅に住まわれるお客様はこんなコトを実現されたいので、こういうプランになりました」という「一般解から個別解へ」の姿勢が分かるように、ホームページやSNSでの見せ方も「あなたならどうされたいですか」を触発する情報発信へ切り替えます。
ご来場時の接客対応と併せて、お客様の暮しを中心とした見せ方と情報発信へ切り替えます。
●ネットで絞って見に行った住宅でときめきとワクワクを提供

「せっかく、わざわざこのモデルハウスや住宅見学会を選んで見に来たのに、私のことを聴いてくれずに自分のしゃべりたいことばかり話す」住宅営業に我慢させられ、もう少しじっくり見たいのに、住宅営業には適当に流して見せられ、後はお金と土地のことばかり聞かれるという苦痛を受けた、と多くのお客様は感じておられます。このような対応は、「どこの会社に行っても同じようなもの」なので、「こんなもんなんだろう」という感覚になっていらっしゃいますが、本来はお客様が実現したいコトを中心に、新しい住いでの「ときめきの暮らしに気づき」、「ワクワクする新しい暮らしへの期待感が高まる」暮らし視点でご案内をすれば確実に受注につながります。
また、この視点のモデルハウスや住宅見学会の案内の仕方を情報発信に応用すれば、集客数は確実に増加し、本気度が高いお客様が集まるという集客の質も向上します。
まとめ
お客様の視点で考えれば様々なことが見えてきます。
コロナ禍の行動様式変化やデジタルネイティブ世代が住宅需要の中心世代化している事を市況環境として捉えて対策を講じましょう。
従来の集客手法や接客応対、あるいはモデルハウスや住宅見学会の作り方や見せ方も視点を変える必要があります。
お客様の暮らしを中心とした視点の新たな住まいづくり方式へ転換を図りましょう。
ハウジングラボでは、お客様の「納得」と「満足」を高めて標準6週間で受注を獲得する、スピード感のある住宅営業手法をご用意しています。
自社特徴の好印象化で「いいね」を積み重ねる住宅営業手法をもとに、住宅事業の安定経営をサポートします。
「商品」「商品開発」「集客・マーケティング」「営業」「設計」「マネージメント」の5分野からなる住宅営業サポートです。
是非ご活用ください。
■ハウジングラボの住宅営業サポート
https://www.housing-labo.com/consulting
住宅事業の安定継続/発展に役立つセミナーも開催しています。
■住宅営業セミナー
https://www.housing-labo.com/seminar
《執筆者》
株式会社ハウジングラボ
代表取締役社長 松尾俊朗
一級建築士










