市況によって上昇する価格に振り回されない住宅営業とは
2024/08/09

ウッドショックから始まり、多くの住宅会社・工務店で坪単価が上昇しています。
「住宅の坪単価が上がったから売れない」というのはプロの世界では通らない話です。
具体策としてどう対処するのかを考えてみましょう。
Contents
価格が上昇した時には、ポイントを絞った住宅営業/住宅設計が重要

漫然とした住宅営業対応と住宅設計対応では、ズルズルと面積も大きくなってしまい、「価格ストライクゾーン」から逸脱してしまいます。
お客様の暮らしの重心を掴み、ポイントを絞って、実現する新しいお住いの魅力をお客様と共有化することが重要です。
そのためには、Max資金計画のお客様との共有化は不可欠です。
ご予算ではなく資金調達力を含む資金準備力の最大値を初回面談時の最後に共有化します。
初回面談で魅力的な住まいづくりを共有化できるのかがポイント

住まいづくりにおいて、お客様のご要望は方向別に3つの軸で構成されています。
1軸:一般的なリクエスト(部屋数、駐車台数などお客様が初期から見えている範囲の要望)
2軸:実現したいコト(せっかく新しい住いになるのだから「これだけは実現したいコト」に気づいていただく)
3軸:価値観の理解(お客様の趣向や大切と思っていることなどについて理解し共有化)
殆どの住宅営業担当者と住宅設計担当者は、1軸のレベルに留まっており、「部屋数と広さ」「キッチンのタイプ」「収納が足りない」などの「一般的なリクエスト」に応えているだけです。
この状態では競合他社と同じようなプランを作成してしまうことになり、同じ広さなら安い方、同じ価格なら広い方、というような「同じような図面上での高い安い、広い狭い」の話になってしまいます。
特に、販売価格高騰時には価格一辺倒の話に陥りがちです。
●「実現したいコト」を初回面談で共有する
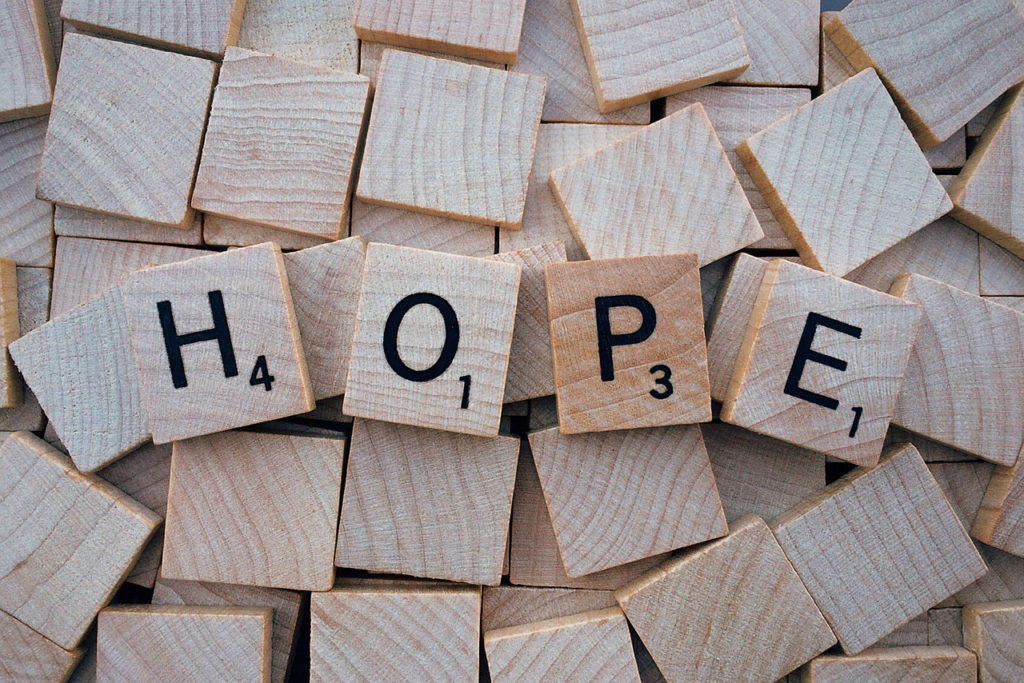
実現したいコトも、収納を多くしたいとか雨天でも洗濯が干せるサンルームだとかの現状の暮らしでマイナス領域を改善する程度の「実現したいコト」ではなく、週末晴れたら夫婦でテラスでアフタヌーンティーをしたい、とかの楽しい暮らし、心豊かな暮らしという暮らしのプラス領域の「実現したいコト」に気づいていただきまます。
●住まいづくりの目玉づくり

お客様ご夫婦が「これが実現できました」と周囲の方々へ言いたくなるような住まいづくりの目玉が必要です。
これから半世紀以上の長い年月を過ごす暮らしの器です。
こういう暮らしを実現しようという「住まいづくりの目玉」を中心に据えて考えます。
本来、住まいづくりはこのように考えて行けば楽しいはずです。
「モノからコトへ」と楽しいことを考えずに住宅というモノを作ろうとするので、眉間しわが寄ってきてしまいます。
もっと楽しい住まいづくりの方向へお客様をリードしましょう。
●「大きなリビング」より「家族が楽しく過ごせるリビング」

「人と人が相手の顔を見ながら普通の声でストレスなく話ができる距離」を「社会距離」と言います。
この距離は1.2~3.6m。
ひそひそ話もできる「個体距離」は0.45~1.2m。
子供を抱いたりあやしたりしている場合は「密接距離」で0~0.45m。
つまり、家族がストレスなく自然なコミュニケーションが取れる広さは実は3.6m四方の8畳空間です。
そうした空間認識も実際にお客様にご家族で体感体験していただいて、その8畳空間にどんな機能が必要なのかの楽しく過ごす工夫を考えるのも「暮らしの目玉を創っていくこと」に繋がって行きます。
●人生に有効な投資をMax資金計画内で行う

お客様ご自身のこれから先の半世紀以上ある人生への投資が住まいづくりですから、「これだけは実現したい」から「こんなことも実現してみたい」と暮らしのプラス領域への投資はMax資金計画内でどこまでできるのか、という発想をお客様と共有化します。
「住まいを楽しみ人生を楽しむ暮らしの実現」という本来の注文住宅事業の本質に基づいて進めるとこのような発想に至ります。「お客様の暮らしを中心に考える」という姿勢そのものが他社との大きな差別化になります。
まとめ
建築資材の高値は自社だけに降りかかるものではなく、全ての住宅業界関係者に共通して起こっていることです。
極端なローコスト層を客層としている場合のみ「需要が消える」こともあるかもしれませんが、それ以外のすべての価格帯の客層で単価の上振れが起こっているだけです。
ただし、従来と同じことをしていれば面積×単価で価格は上昇しただけになります。
それが新たな付加価値という個のお客様から観て魅力的なものになっているなら、お客様はMax資金計画内で「魅力の対価」を支払われます。
「一般解の住宅で価格競争」という時代ではありません。
エンドユーザーに主導権が移った今日では、個のお客様の実現したい暮らしへの対応という注文住宅事業本来の考え方を磨きこむ好機だと思います。
《執筆者》
株式会社ハウジングラボ
代表取締役社長 松尾俊朗
一級建築士











