間違いだらけの注文住宅事業
2024/08/16

過激な表題ですが、正確に表現すれば、注文住宅を発注する側のお客様が軸を持たずに住宅会社へ注文を出しているため、予算は低めで、要求はランダムかつ過大になりがちです。
それに振り回されているのが現実だと思います。
注文住宅は、お客様から明確なオーダーがあって初めて家というモノづくりの住宅会社はその機能を十分に発揮することができます。
ユーザーの住まいづくり情報が未整理状態での発注が、最大の間違いをもたらせています。
Contents
お客様の住まいづくり情報の整理がポイント

モノづくり側である住宅会社へ発注する際のお客様の要求内容が未整理という事が混乱を招く原因であることは明白です。
それは果たして住宅営業の仕事でしょうか。
住宅営業担当者は、住宅という商品(モノ)説明が基本業務。
それに見積提示が加わり、あとはお客様の支援業務として資金計画作成/金融機関の手続き、土地の紹介と敷調や役調。
さらに、お客様の窓口業務としてFP、住宅設計、IC(インテリアコーディネーター)との橋渡しなど。
あとは手続き業務ですから、「モノづくり営業」の範囲にとどまるのは当然で、「お客様の住まいづくり情報の整理」という業務は本来、住宅営業業務の範囲外です。
お客様側の住まいづくり情報を整理する部門は存在しない
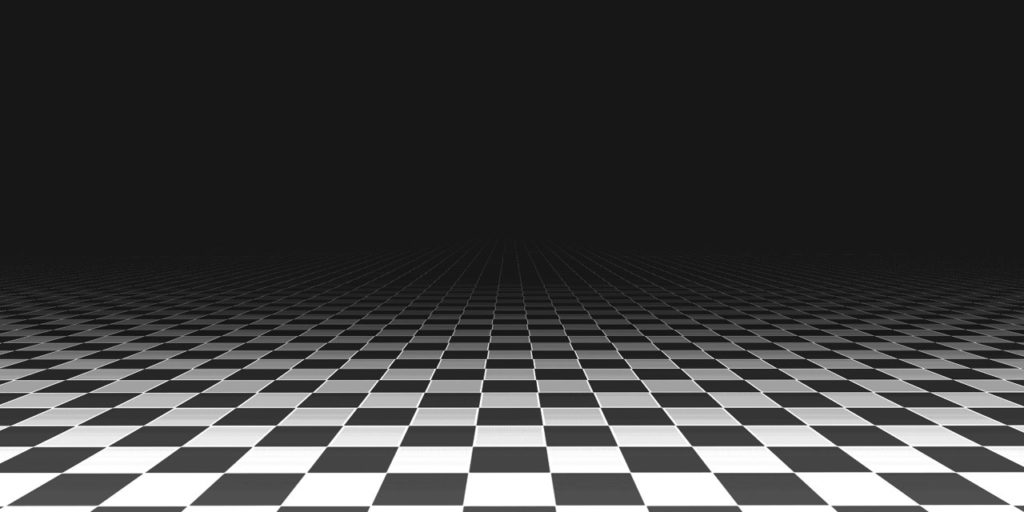
ハウスメーカー、工務店はモノづくり企業です。
お客様の要求に従って家を造るのが本業です。
住宅設計にしても、お客様の要求を如何に予算内に、敷地内に収めるのか、という事が主な業務になります。
ICも経産省の主旨で言えば「販促係」ですから仕様選びです。
住宅営業、住宅設計、ICという役割の中に、ユーザー側の住まいづくり情報を整理する部門は存在しないという事になります。
●受注生産方式が注文住宅事業の根本問題

注文住宅事業は受注生産方式をとっていますので、「住宅設計/デザイン・見積」のお客様との合意がない限り、生産へ移行(着工)するわけには行かず、何度もプランの変更があると「儲からない事業」に陥ります。
「モノづくり事業」の上流の「お客様の住まいづくり情報の整理」を住宅営業に付加するのか、新たな職種として設定するかという選択になります。
これが出来れば、「建築というモノづくり」に住宅営業も住宅設計もICも、もちろん工事も集中でき、生産性は大きくアップし儲かる事業へ発展します。
●ご自身の暮らしが見えていないお客様と向き合う

「注文住宅事業は目に見えないモノを売るビジネス」ですから、マンションや分譲住宅とは異なる難易度の高いビジネスと言われてきました。
モデル住宅などで見える化の努力を積み重ねてきましたが、本当の問題は「自分の暮らしが見えていない」お客様側にあったという事です。
ここへの対策を打たない限り問題は解決しません。
では、現実的にどのような方法があり、どう対処すればよいのかという事になります。
どうやって、誰が、ご自身の暮らしが見えていないお客様と向き合い、実現したい住宅の住まいづくり情報をまとめるのか。
現実的な方法が必要です。
●住宅営業本体業務の柱に据える

「お客様の暮らしを中心に考える」という考えの基、お客様に「ご自身の暮らしに気づいていただき新しい住いで実現したいコトは何か」とお客様と一緒に考えて方向性を共有化する機能を住宅営業本体機能に加えます。
既にいくつかの住宅会社では「気づき共感営業」として「お客様にご自身の暮らしに気づいていただき」、そこを起点にお客様の実現したいコトを共有化するという住宅営業方式で成功している会社はあります。
この場合、一番難しいのは、実は「お客様を中心に考える」という発想の転換です。
スローガンとしては顧客中心と言っていますが、多くの住宅会社は「自社中心主義の住宅営業」です。
例えば、自社工法の断熱気密性の良さをアピールするのは自社中心主義です。
お客様中心であれば、断熱機密性能が上がったからどのような暮らしが実現できるのか、という視点はお客様視点です。
「断熱機密性能が上がると冬布団が不要になって、収納がその分楽になります」というようなユーザーメリットです。
もう一歩進めると、このような一般解ではなく固有名詞のお客様が実現したいコトへのメリットの提示です。
具体的には、お子様が思春期を迎えても家族が仲良く暮らしたいと願っているお客様には、「断熱機密性能があがるとプライバシーを必要とする以外はドアを閉めなくなる暮らしに変わり、家族が互いに気配を感じるようになり、より仲良くなった」とか、具体的なお客様メリットです。
●住宅営業の進化が注文住宅事業の未来を拓く
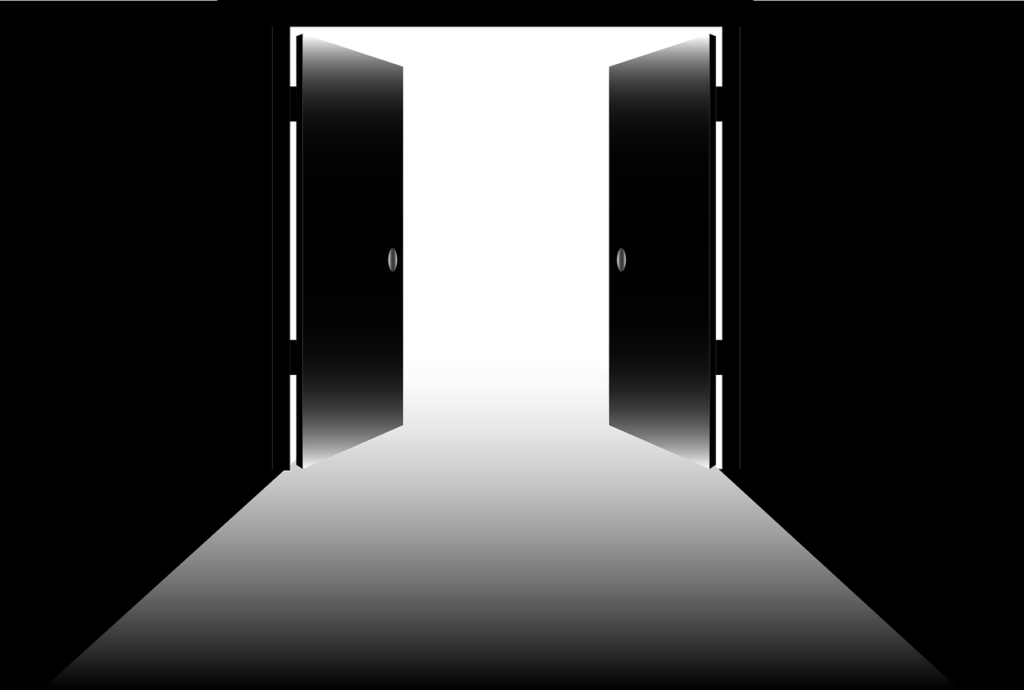
モノづくりのプロセスに入る前段階の「こういうモノ(家)にしてほしい」というお客様の要求をまとめることができれば、注文住宅事業の生産性は上がり、「他社との大きな差別化」が可能になります。
次世代の注文住宅事業は、この「ユーザー側の住まいづくり情報を整理する」部分にあります。
この分野を切り開くことは、ユーザーから高い評価を受けて成長軌道を進むことができます。
まとめ
素人のお客様に「どのようなプランになさりたいですか」と問うても的確な回答は出てきません。
その回答に従ってプランを作ってもプランが決まるはずはありません。
このような「間違いだらけの注文住宅事業」から脱却を図りましょう。
具体策も用意されており、実績もある営業手法を導入して「お客様側の住まいづくり情報を整理する」という、より上流での住宅営業を推進することで、営業効率、設計効率は各段に向上します。
「次世代の正しい注文住宅事業」へ進みましょう。
《執筆者》
株式会社ハウジングラボ
代表取締役社長 松尾俊朗
一級建築士











