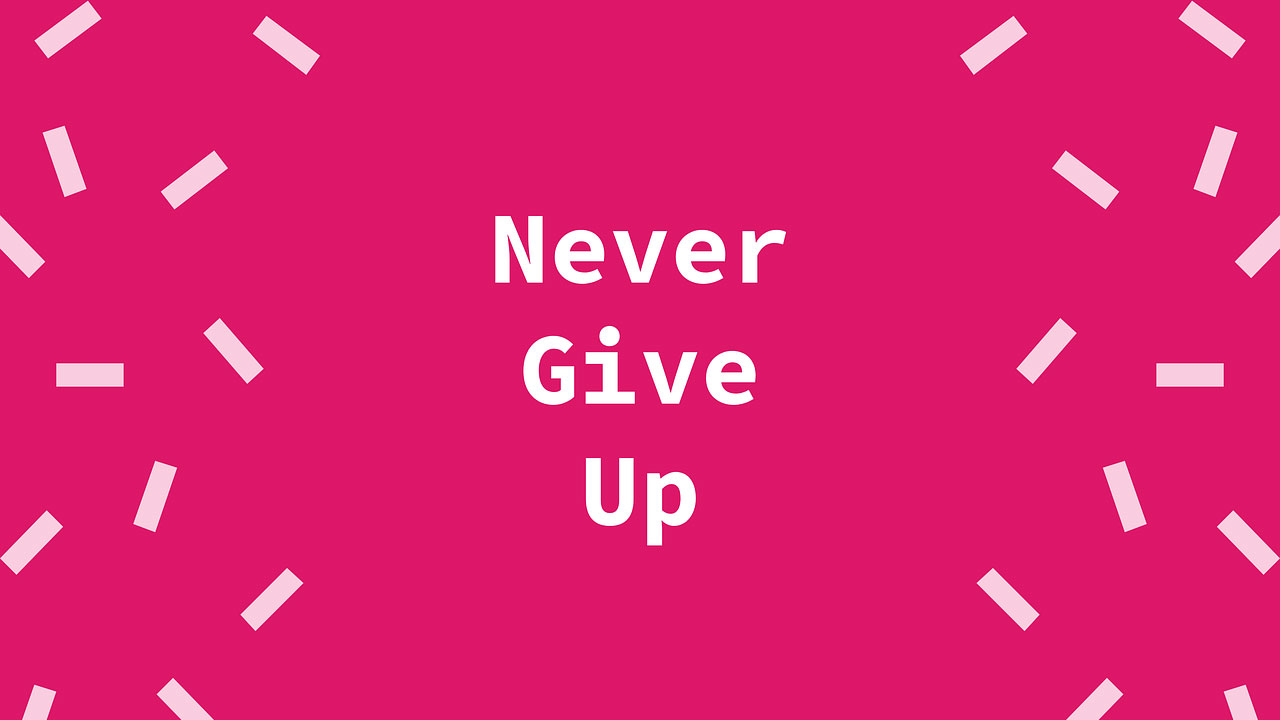小さな家の豊かな暮らし
2024/07/26

1950年代の2DKを起点に4LDKまで部屋数と共に面積が拡大してきた日本の住居。
気が付けばアメリカに次いで世界第2位の住宅の広さを手に入れました。
それでもエンドユーザーは「もっと広く」の要求が続いていまます。
この声に応えていくことが正しい住宅づくり方向なのか考えてみたいと思います。
Contents
なぜ床面積と部屋数が増えたのか

全て和室が基本の戦前は15坪ほどの住居で特に不自由は感じなかったそうです。
和室の持つ多用途性が、コンパクトで便利な住まいを実現していました。
卓袱台(チャブダイ)を転がして置けば、ダイニング。
布団を敷けば寝室に早変わりです。
戦後の洋風化の流れの中で各部屋が用途専用化されて来たために、寝室のように寝ているときだけしか使わないため殆どの時間はデッドルームとなってしまい、部屋数が増え、結果として面積も増加してきました。
モノが多い日本人の暮らしも影響

世界の中で物質的に最も豊かな生活をしているのが日本人かもしれません。
食事でも、朝食はトーストにハムエッグ、昼食はざるそば、夕食はイタリアンと、3食で世界一周しても全く違和感なく世界中の食事を取り入れていますから、その分キッチン周りの食材、食器、調理器具、家電、カトラリーの収納は多くなりがちです。
衣類も女性は春夏秋冬を楽しみ、ファストファッションから冠婚葬祭用迄、一般的にかなりの衣装持ちです。
多様な食文化、ファッションに敏感な文化など、日本人の多様な文化を取り入れてしまう文明吸収力が影響しています。
したがって、収納も大きな関心を集める部分であるため面積拡大の要因になっています。
すっきりした空間を好むユーザーも多い

モノがあふれる一方で、物はすべて隠してすっきりした空間が欲しい、というリクエストが多いのも昨今の特徴です。
タタミと障子のすっきりした直線ラインの何もない空間を好むように日本人のDNAには組み込まれているのでしょうか。
江戸は大火が多く、物は持たずに土間に茶碗と箸を埋めて大火の際には避難したそうです。
極端にモノがない生活ですが、暮らし満足度は高かったようです。
かけそば1杯分の値段で写楽の浮世絵が買えて壁には貼っていたのですから、都市部の庶民の長屋はシンプルでも豊かな空間だったと思います。
このDNAも日本人には受け継がれているのかもしれません。
ル・コルビジェの「小さな家」



1923~24年に、20世紀の建築界の巨匠ル・コルビジェが両親のために建設したスイスのレマン湖畔の「小さな家」は、わずか18坪ほどの小住宅ですが狭さを感じさせません。
3度訪れましたが、レマン湖を挟んで遠くにフランスアルプスが見渡せるという絶好のロケーションも効いているとは思いますが、それにしても狭いと感じないのは何故でしょうか。
完成後、父親は直ぐに亡くなりましたが、母親は100才まで悠々と息子が贈ってくれた小住宅での暮らしを楽しみながら住み続けたそうです。
モジュロールというコルビジェが考えついた身体の各部の大きさを考慮して設計するという概念の上に、さらに「自分の母親」という個の暮らしを考えて、「本当に必要なモノといきいきと生きて行くために心に必要なコト」について考え抜いたプランは、「無駄はないが心に余裕をもたらす18坪の小住宅」です。
無駄を省き余裕を与える

言葉では簡単ですが、これを実現するのは相当に難しそうです。
100年前に実現できた「小さな家」は、その考え方の再発見の時期に来ているように思います。
「無駄なモノは何か」「心の豊かさのために必要なコト」は何か、と言う視点は改めて新鮮です。
ダイニングテーブルを食事にだけに使っているのは無駄でもっと活用できないか。
確かにダイニングは子供の宿題をする場にはなっていますが、機能が不足していないか。
寝室は寝ている時間だけしか使わないのはもったいなくないか。
寝室をオーディオルームや在宅勤務の書斎として収納やスペースの取り方を工夫できないか。
玄関とは、そもそも靴を脱ぐところなのか格式の場なのか、あるいは日曜大工のスペースなのか。
様々個々のエンドユーザーの暮らしと価値観に照らして考える段階に来ているのだと思います。
固定概念を捨て去ってユーザーと向き合う住まいづくり


和の住まいは畳の空間ですから、その多用途性でお客様の暮らしを考えなくてもユーザーが座布団や、卓袱台、布団という小道具の出し入れで個人が勝手に住まいを用途に応じてコーディネートして使っていました。
洋間中心の現代の暮らしでは、各部屋が固定概念的に用途が限定されていますから、本来どう使うのかをよく考える必要がありますが、ユーザーのことをよく見ていないというのが現状です。
4LDKというワンパターンに縛られてしまって、お客様の暮らしを中心に置いて深いところで考えていないということに慣れきってしまったようです。
まとめ
改めて目の前のお客様という住宅のユーザーの価値観という視点で「無駄を省き」「心豊かなコトに気づき」それに基づく住まいづくりを進めると、固有名詞のついた「2022年版小さな家」にたどり着くと思います。
2DK誕生から70年の2022年は脱4LDKを考える年になってほしいと願っています。
大きいだけが良い家ではないという未来の住宅の姿がそこにあります。
《執筆者》
株式会社ハウジングラボ
代表取締役社長 松尾俊朗
一級建築士