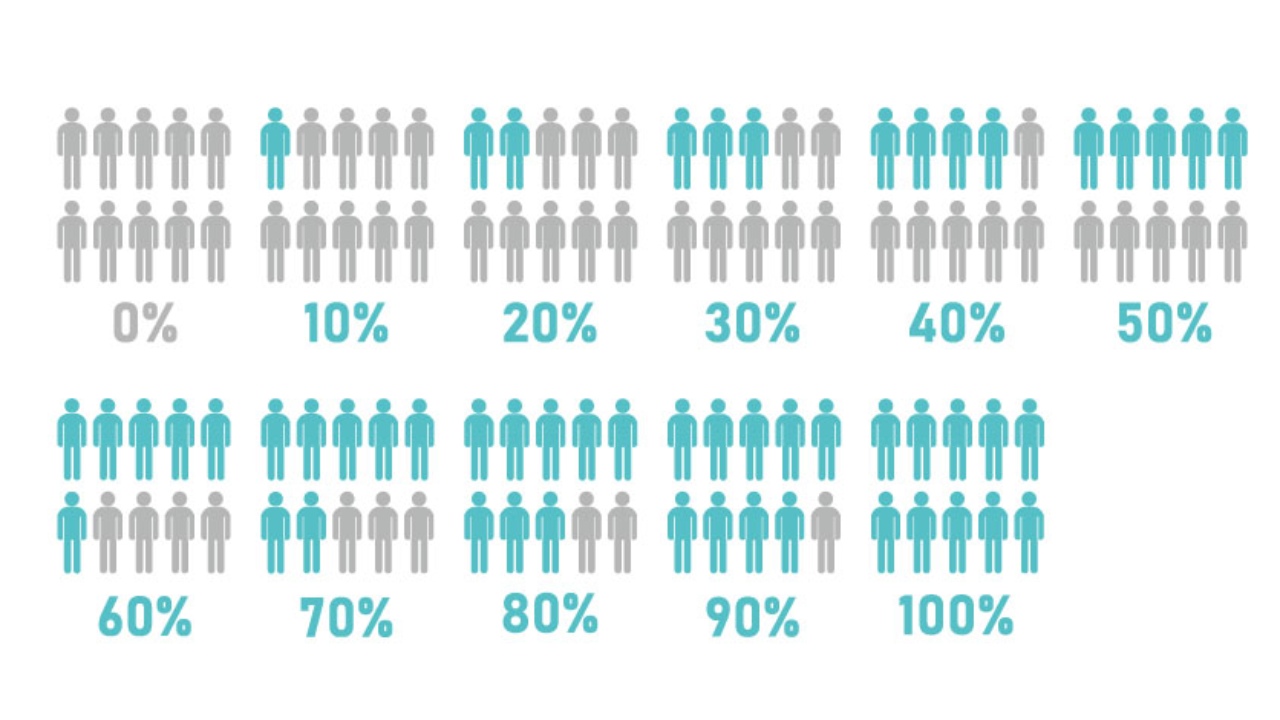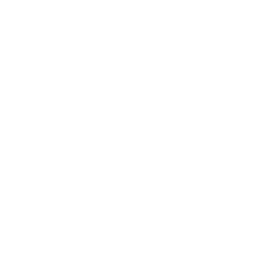住宅設計のポイントは「コンパクトに広く」
2022/03/01

住宅設計を進める一つのポイントが「コンパクトに広く」という設計の考え方です。
3帖一間の暮らし、外国人にも人気のカプセルホテルなどコンパクトな空間は囲われ感があってしかも手が届く範囲にすべてのものがあり、至って便利な空間です。
これが毎日となるとさすがに閉塞感に繋がります。
このコンパクト空間の良さ、便利さと開放的に感じる空間構成が「コンパクトに広く」という設計の考え方です。
Contents
広いか狭いか

お客様は同じ価格なら広い方が良いと大きな床面積を要求されます。
図面の上では広い方がより「得した感じ」があるのも確かです。
面積が広くても空間として狭く感じるということはプロの設計者は分かっていますが、素人のお客様や営業は「もっと広く」の大合唱です。
「コンパクトに広く」とは、物理的にはコンパクトで便利だが広く感じる空間づくりのことを指しています。
茶室のように小さなにじり口から入るとわずか2畳の茶室空間がとても広く感じるような時、逆の発想で敷地から見える遠くの山並みを借景として屋外空間に取り込んで限りなく広く感じさせるなどというように、日本の空間設計では「コンパクトに広く」というテクニックが満載です。
居心地の良い空間

一般に居心地の良い空間とは思った以上に狭い空間です。
3.6m×3.6mの8畳空間は、家族で過ごすリビングとしては互いの表情もはっきり認識できて、普通の声で話しても細部まで聴きとれます。
4~6人家族には居心地の良い空間です。
ところが、一般のお客様はもっと広いリビングを要求されることが多く見受けられます。
もっと広くもっと広くという要求は近年特に強まっています。
その要求に従って大きな空間を設計することが設計者の対応として良いのでしょうか。
心地よい空間を放棄していることになります。
●心地よいとストレスを受けるは同居

確かに8畳の空間は心地良い居間を創る適切サイズですが、家族もいつでも仲良しというわけでもありません。
人間ですから多少のぎくしゃくした関係になってしまう一時期もあるでしょう。
そうしたときには「近すぎる距離」となり「8畳空間はストレスの逃げ場がない空間」になってしまいます。
「心地良さ」と「ストレス」が同居してしまいかねない空間です。
●開放的に感じさせる工夫

適度に狭い空間は居心地が良いのですが、ストレスも受けやすいとなると何らかの対策を打つ必要があります。
視線を外せば他の空間にまで視界が伸びる工夫が必要です。
リビングなら外部空間と視覚的につながった広く感じる空間づくりです。
他の空間からの動線を外した位置にリビングを置いて、視覚的には開放感を与えたとすれば「コンパクトに広く」という考えを実現できそうです。
居心地がよくストレスフリーな空間

「適度な囲われ感」と「視覚的な開放感」を持つ空間を作ることが、居心地が良くてストレスフリーな空間づくりです。
外部に視界を抜けさせることができれば外部空間も活用します。
内部空間でも、いくつかの空間を横断的に視界を確保すれば、それも有効な設計手段です。
高さ方向の開放感として吹き抜け空間やその先の空間を視覚的に利用するのも有効です。
●部屋の使い方で選択
水平方向の隣接する空間を取り込んだ開放感、水平に外部空間を活用した開放感、高さ方向への開放感等どのようなテクニックを採用するのかは、その空間の使い方を考慮して決めます。
来客が多い場合は、あまり隣接する空間を取り込むというのは家族のプライバシー上好ましくないとか、様々な日常生活場面とその頻度でどのように「コンパクトに広く」となるような設計をするのか方針を設定します。
●空間は感じ方で「サイズ感が決まる」
実測上の広い狭いは実はあまり関係がなく「広く感じる」か「狭く感じる」かの判断ということになれば、図面での検討にいきなり入るのは誤解を生んでしまう可能性があります。
設計打ち合わせはモデル住宅で行うというのが、お客様の空間の感じ方の体感体験を通した正しい結論を導き出しやすいのでお勧めします。
まとめ
「コンパクトに広く」とはなかなか一筋縄で身に着けられる設計技術ではないのですが、実際の空間認識力と設計力を一致させて、お客様の暮らし方にも応じた自在な空間設計に欠かせない技術です。
特に狭い敷地が多い日本の限られた延床面積の中で暮らしにフィットした住宅設計のためにも必要な考え方です。
《執筆者》
株式会社ハウジングラボ
代表取締役社長 松尾俊朗
一級建築士