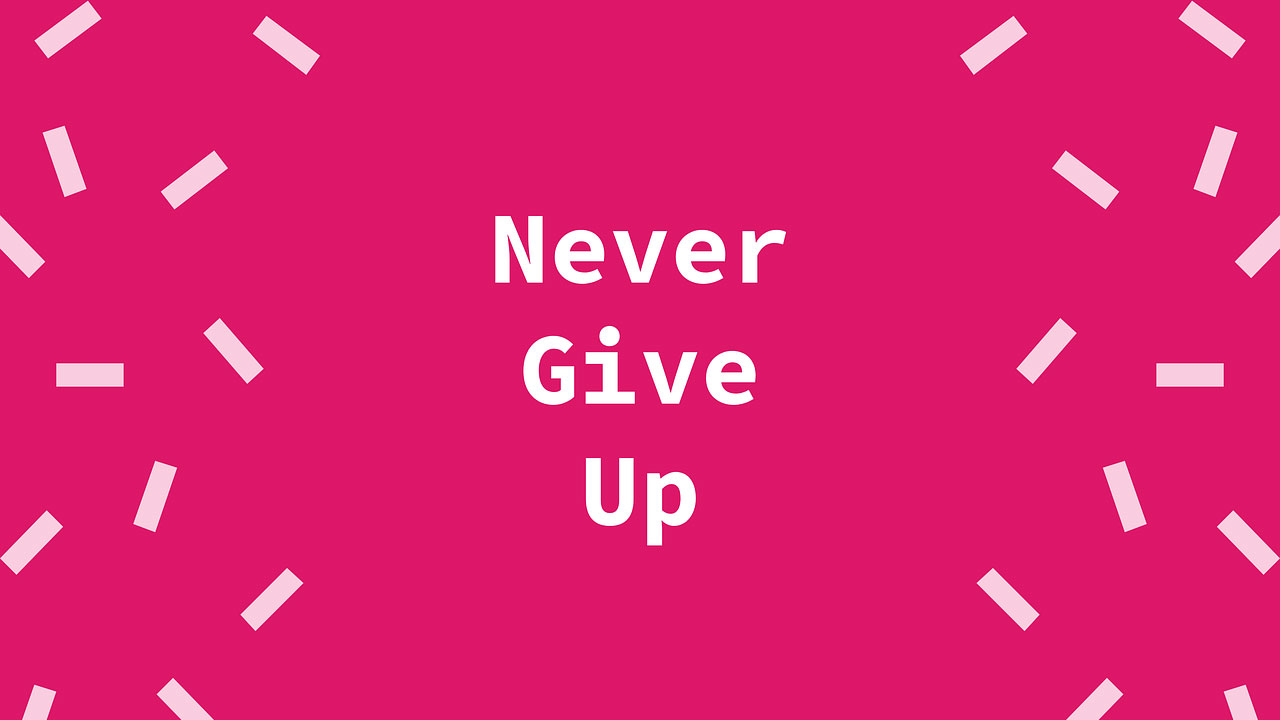視線の制御という住宅設計技術
2022/01/25

建築設計は「空間をいかに仕切るか」という技術と言えます。
西洋建築は「壁勝ちの建築」ですから内部空間を壁で仕切ってドアとか窓の開口部を設けるという考え方です。
日本の建築は「柱勝ち建築」ですから柱以外の壁はなく襖や障子の建具をはめ込こんだ「簡易な壁」で空間を仕切るという空間の作り方です。
視線は遮っても声などの音は通しますし、仕切りを開けようと思えば簡単に開けることも可能です。
建具の開閉とはめ込みで大空間でも細かく仕切ることも可能な「可変空間」を手に入れてきました。
それでも空間の仕切りが成り立ってきたのは「結界」という考え方で「許可なく開けてはならない」という不文律で空間は仕切られ、家族内のプライバシーもそれで成り立ち制御されてきました。
視線を遮る、視線を通すという「視線の制御」が「結界」概念と共に日本の建築では自覚なく重視されてきました。
Contents
LDK空間への拡大要求

お客様の要求で「リビングを広く」というご要望は年々大きくなっています。
LDKは一体空間である場合が多く、実際には「LDK空間が大きく感じる」ことと、お客様の要求を解釈しても良い場合がほとんどです。
もっと広くとの要求に応えるためには、絶対面積では限度があるため「広く感じる」設計をします。
いわゆる「視線の抜け感」「広く感じる工夫」という「視線を制御」することが重要な設計要素になってきました。
外部空間の取り込み

遠景までを取り込む「借景」という外部空間の取り込み技術は「視線を無限大」近くまで拡げる設計技術です。
そこまで大掛かりでなくても視覚的に空間を拡げる設計技術を有効に使います。
狭い外部空間でも内部空間とつなげてを広く感じさせる視線制御

京都のある料亭の空間です。
サッシ枠を消して空間をフラットアウトさせ、外部空間へつなぐことで視線を庭へ誘います。
隣地までの奥行きは思いの外短く狭い庭ですが、小石、竹、竜のひげ、生垣などで「奥行き感」を感じさせる設えをしています。
実寸としては隣地が近いため本当なら隣家が見えてしまいますが、簾を下げて上部の視界をやわらかく遮って余計なものが目に入らないように視線を制御しています。
「視線の制御という設計技術」で広がり感ある空間を生み出しています。
視線制御で空間を拡げる工夫

同じく京都の和菓子店の地窓です。
左の画像は室内側から外部へ広がり、右の画像は外部からは内部空間へとつながっており「広さ」を感じさせています。
実はこの小さな庭の灯篭の外側に嵌め殺しのガラス建具があり、温熱環境は内外で分けていますが、空間的な連続性を上手な視線制御技術で獲得しています。
この和菓子店の外部空間は、ご覧のように人一人が通るのが精一杯という通路幅の路地です。
この路地を外部空間として最大限に取り込むという高度な視線制御技術を持った設計です。
隣地との50cmでも視線制御で空間は広く感じる

京都の老舗旅館のバスルーム。
隣地との僅かな空間を使って心地よい浴室を生み出しています。
隣地からの視線も巧みに遮りパーソナルな空間を構成しています。
視線制御技術は重要な住宅設計技術
お客様の「絶対的広さ」の要求に「敷地面積などの制約条件」を踏まえた上で、十分に応えていくのがプロの設計です。
「視線の制御技術」は設計者の諦めない設計に対する粘り強い創意工夫の上に成り立っています。
住宅設計者として「視線の制御」で心豊かな暮らしの実現を目指します。
LDK空間での会話と視線制御
住居空間内で「ふつうの声で会話」できる距離はせいぜい3.6mです。
この距離を超えると「互いの話がよく聴き取れず」ストレスを生む原因にもなります。
「会話可能な空間」と「細かな会話はできない」が「おおむね何を言われたかわかる空間」、「存在を視界にとらえてさえいれば同じ空間にいることを認識」できるのでそれで充分という空間サイズなど「連続する空間の区分を明確にしてお客様の暮らし最適空間を設計」します。
「会話と視線の制御」は住宅のメイン空間であるLDKを設計するときの重要な要素です。
まとめ
一般的な住宅設計において建築与条件は、敷地サイズ的にも予算的にもそれほどゆとりあるものではないはずです。
お客様の価値観に応じた「住まいを楽しみ人生を楽しむ暮らしの実現」を実現するためには、「視線の制御という住宅設計技術」を身に着けて、より高次元でお客様に魅力ある空間という付加価値をお届けします。
暮らしの多様化が進み要求が厳しくなる現在の住まいづくりにおける設計者の使命です。
《執筆者》
株式会社ハウジングラボ
代表取締役社長 松尾俊朗
一級建築士