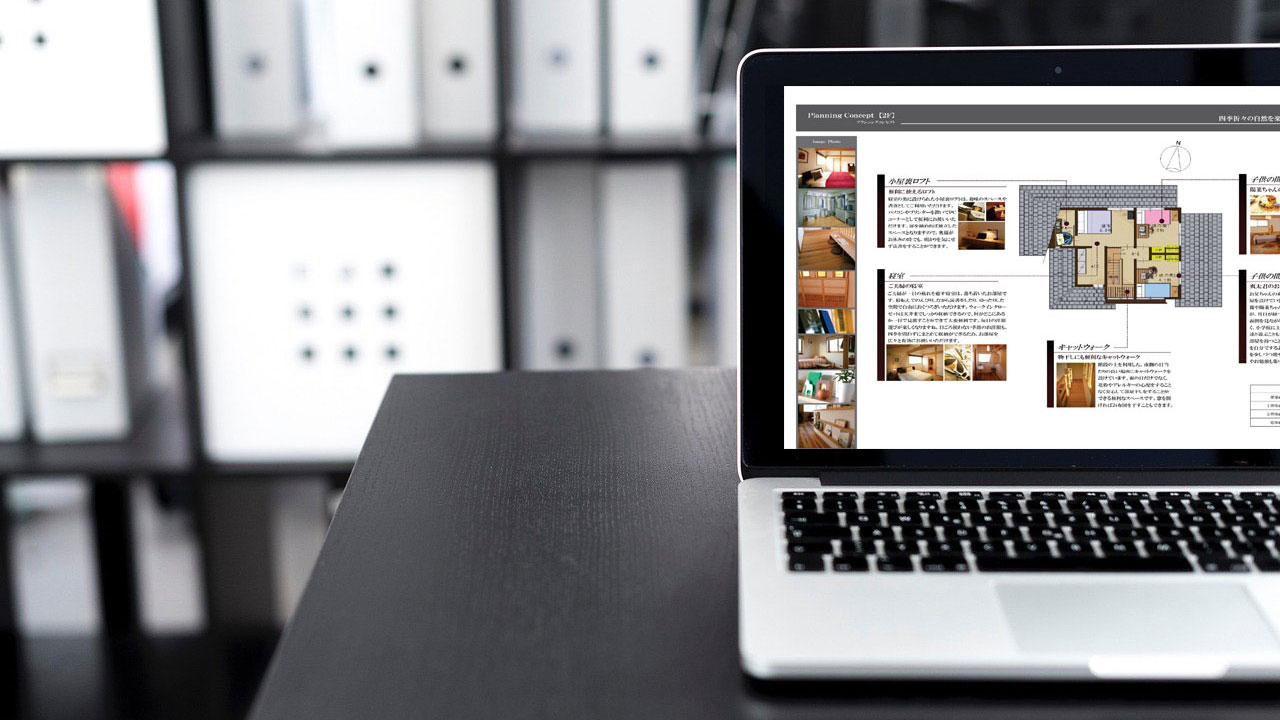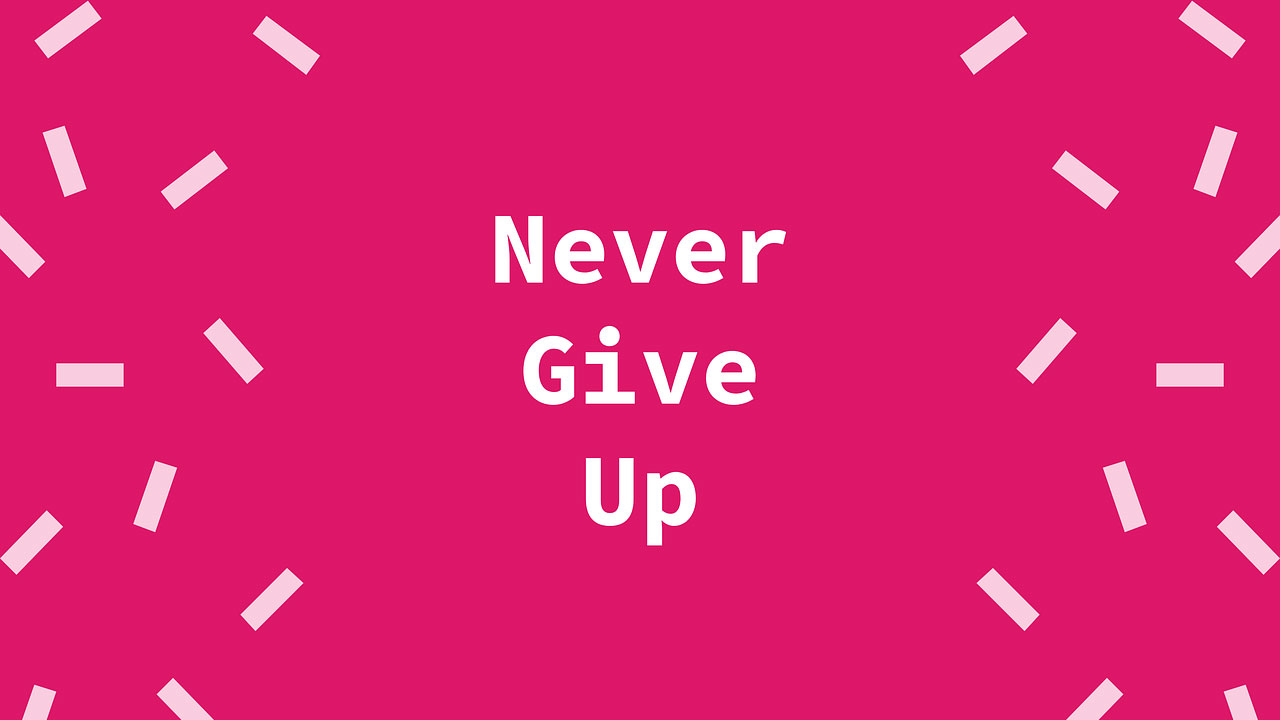住宅設計の打ち合せは、1/100の図面より実物空間の方が効果大
2022/02/27

住宅設計者は、まず基本計画として1/100の図面で全体プランをまとめると思います。
この図面を用いて、お客様とのお打ち合わせは、実際にはお客様にどの程度伝わったのかというと、ほとんど伝わっていないというのが実際のようです。
それならいっそ最初のヒアリング/インタビュー時からプレゼンテーションまで、モデル住宅などの実物空間を使ってお客様と向き合えば、「こうしたい」というお客様の意図も理解出来て、それに基づいて作成したプランの意図も共有化しやすくなります。
実物空間のフル活用はいかがでしょうか。
Contents
住宅会社の設計ならではのお客様との向き合い方

設計事務所の設計者ならヒアリング時は事務所ですし、プレゼンテーション時も図面と模型、CGそれにせいぜいVRくらいが、お客様への設計意図を伝える手段です。
これに対して、モデル住宅などの実物空間を使えるというのは、住宅会社の設計の優位さです。
この優位さを単に2次元の平面図を3次元で補足できるというレベルの使い方ではなく、「お客様が実際に暮らすとして」という「日常の暮らしの質の高さ」という視点でお客様と向き合い、ご理解いただくために使います。
実物空間で暮らしを考えての住宅設計

お客様に、設計したプランを伝える段階だけ実物空間を利用するだけではなく、住宅設計情報をお客様から吸収する段階でも、実物空間を使いながら暮らしの実際の場面での使い勝手や居心地の良さを確認しながら設計すべきでしょう。
住宅設計者には、場面ごとのある程度の必要なサイズ感は既にお持ちのはずです。
特にベテランになればなるほどそういう経験の蓄積は多いはずです。
それを活かすもの重要ですが、実際の使用状況を固有名詞のお客様のご家族一人一人を考えて、その動きや座っている状況は案外頭で考えるのと実物空間では差異が生じやすいものです。
●20世紀の名建築の意外な実物空間に驚かされる


「落水荘」と言えば、FLライト作の20世紀最高の住宅建築の一つです。
写真と図面では何度も見ていましたが、実物空間のリビングを体験して驚きました。
天井高が2mしかないのですから。
案内をしてくれたアメリカ人は196cmでしたから、髪の毛が天井に擦れてました。
リビングに座ってみると「ちょうど心地よい高さ」で、おそらくこれ以上天井が高いとこの居心地の良さは手に入らなかったと思います。
図面だけで検討していては、FLライトも施主のカウフマン氏も高身長でしたから、こうはならなかったと思います。
図面と頭の中だけで考える住宅は、使い勝手や居心地の良さを生み出さないと言えるかもしれません。
●お客様ご家族が暮らしの主人公

お客様のご家族は一人一人に個性があり体格も違います。
同時に複数の方が動かれる場面もあるでしょう。
様々なシーンと動きを想定して設計していると思いますが、実際にモデル住宅で動いていただき動線的に使いやすいのか、動線内にある収納は出し入れしやすいのか、高さや動作を確認します。
お客様ご家族が主人公ですから、お客様のご評価に耳を傾けます。
●ストレスフリーな住まい

収納の不満や部屋数などの要求はいろいろあるとは思いますが、総面積的にも余裕がないケースが多いと思いますので、優先順位をつける必要が出てきます。
この場合、何処を優先して何処を妥協するのかは「お客様の動きを見て観察」します。
お客様に優先順位をお聴きすると「全て優先」と言われかねません。
「住宅設計者は暮らしの観察者」です。
住宅設計者が「ここだけはゆとりを持たせて優先しましょう」と提示しますが、その理由も明示します。
使用頻度や家族全員にかかわる場所など、その根拠を示します。
同じように「圧縮」する部位の根拠も、年に何回かしか使わないものを入れる収納部の使い勝手は「いじめる」とかも明示します。全体として日常生活はストレスフリーな状況を少しでも生み出すように考えて実物空間で確認をしていきます。
●ヒアリング/インタビューとプレゼンは実物空間で

お客様との面談は、事務所での打ち合わせより可能な限り実物空間で行います。
これを習慣づけるように意識しましょう。
住宅設計者がお客様と面談する場は、大きくは「ヒアリング/インタビュー」時と「プレゼンテーション」時だと思います。
この2回を確実に2回で終わらせることを目指します。
納得度の問題ですので、実物空間での体感体験は重要です。
実物空間を利用せず事務所での打ち合わせと図面等でのプレゼンテーションでは、何度もプラン変更を繰り返すということがよくあります。
何度も変更を繰り返すうちに、そもそもどういう考え方で設計してきたのかという根幹の軸ブレが始まり迷走します。
一旦迷走しだすと収拾がつかなくなり、設計変更を繰り返します。
こういう事態に陥らないためにも、実物空間を有効に使いましょう。
まとめ
住宅設計担当者は、「お客様の暮らしの器」を設計していますので、「お客様の生の暮らし」を実空間活用で上手に組み立てて行きましょう。
「百聞は一見にしかず」ですが、「図面の100見は実空間の1体験しかず」です。
住宅設計のための経営資源としてのモデル住宅を最大限有効に使いましょう。
《執筆者》
株式会社ハウジングラボ
代表取締役社長 松尾俊朗
一級建築士