【住宅営業が持つべき視点】変化し続けるお客様の暮らしを見つめる視点
2022/09/23
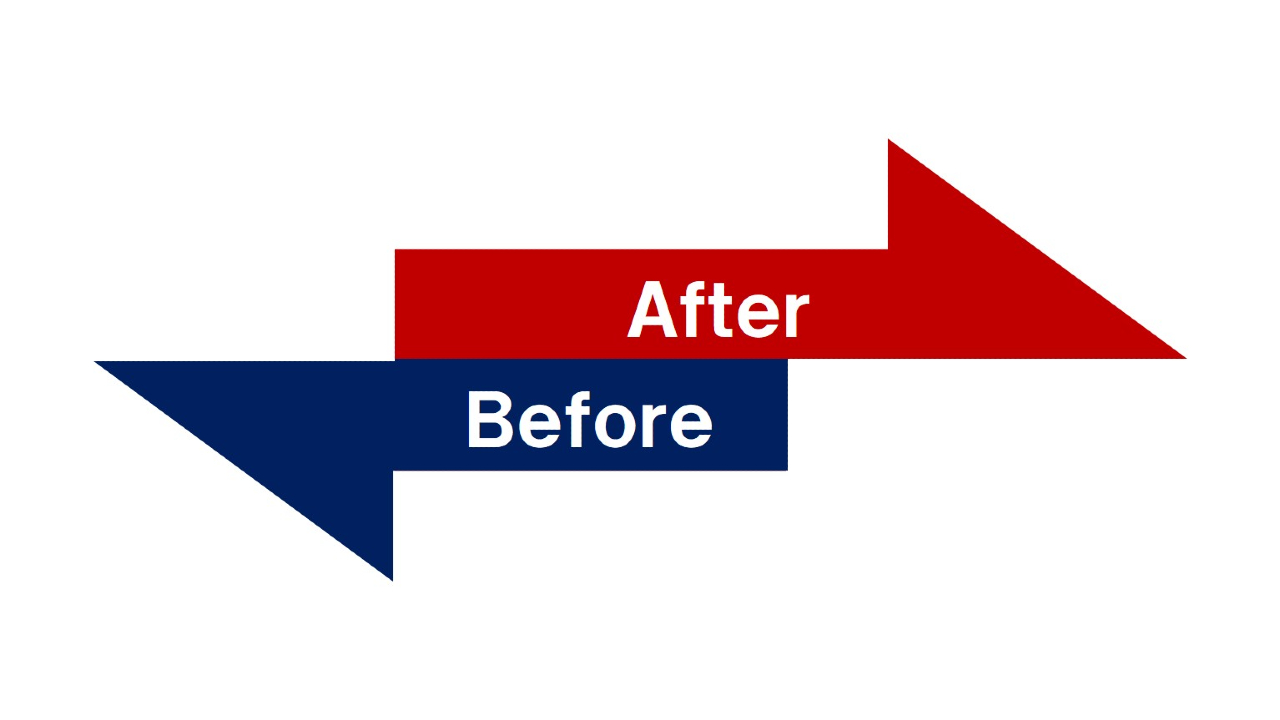
住宅営業やお客様ご自身も気づかないうちに、家族関係・夫婦関係・親子関係などの家族とのつながり方やリビングダイニング・それぞれの部屋での過ごし方が従来とは変化ししています。こうした変化に対応してこそ、お客様中心の住宅営業といえます。
今回は、暮らし方の変化や社会現象の変化しつづける暮らしを見つめる視点とこれに対応して受注を上げていく住宅営業について考えてみます。
社会現象・情勢の変化

ご夫婦共働き率は30年前の1989年には42.3%だったのが、2019年には66.2%と増加し続けています。
現在40歳以上の男性は家庭科が必修ではありませんでしたが、39歳以下の人は男女ともに家庭科が必修に変わり、子供のころから「料理する」ことに触れてきたため、家事は女性の役割という意識も薄れています。
子どもたちは、学習塾で夜遅くまで勉強しています。
働き方は、9時から18時までなどの就労が主流ではありますが、深夜の業務に就く人(工場・小売店・医療・介護現場等)は20.7%います。
世帯構成は、標準世帯と言われるご主人様・奥様・子ども2人という4人家族世帯は、全世帯のわずか4.6%の少数派になり、1~2人世帯が全世帯の2/3以上を占めています。
1~2人世帯の内訳は、結婚しない人・シングルマザー(ファザー)親子・80歳の母親と50歳の息子など多種多様です。
暮らし方の変化

リビングは、家族全員でのコミュニケーションの場と捉えられがちですが、現在は、リビングに家族全員が揃っていても、スマホを操作していたり、テレビを見ていたり、ゲームをしていたりと、みんなリビングにいてもそれぞれ違うことをしている場になっており、コミュニケーションの場とは言い難い部分もあります。
コミュニケーションの場と考えると、従来は料理をする場であったキッチンが、家族や仲間と会話を楽しみながら料理をする場の位置づけになっています。
ダイニングは、食事をする場以外にも、子どもが勉強をする・趣味を楽しむ・くつろぐ等の場としても使われています。
上述した、共働き夫婦の増加や子どもの学習塾などの影響で、夕飯は家族全員揃ってという光景も以前よりは減少し、その代わり、朝食だけは家族揃って採るというご家庭も増えています。
お客様の変化に気づくために

住まいは、お客様の暮らしにフィットしたものであるべきと考えます。住宅営業は社会の変化の傾向を鑑み、お客様の「変化しつづける暮らしを見つめる視点」を持って、その変化に対応した住まいづくりの情報提供をすることがポイントです。社会の変化や暮らし方の変化といっても、難しく捉えて統計情報を調べたりする必要はありません。住宅営業ご自身のご家族状況や同僚・友人・知人などとの会話やニュース・新聞などの情報からでも充分に情報は得られますし、ご案内されたお客様をご案内する際の会話からも情報を得ることは可能です。各方面から得た情報を「へぇ、そうなんだ」と聞き流すか、「そういえば、そうだな。○○○さんもそうだし、先日ご案内した△△△様もそうだった」などと実際に見聞きしたことを思い出し、「変化」という事象とリンクさせて考えることが最初のポイントです。つまり、住宅営業ご自身が、常に「変化というアンテナ」を張って意識していると、自然に「変化」として認識できるようになります。
お客様視点の営業で受注する

例えば、ご夫婦揃って料理と後片付けをされているお客様の場合、「キッチンは料理を作るところ」という考え方から「コミュニケーションを自然に生み出す場」として位置づけることもできます。自然に会話を生み出す工夫として、「南側(立地条件によって、最も環境の良い方位)にキッチンを据え、アイランド型キッチンにすることで、周囲に自然に人が集まるようにする」という情報提供が有効になる場合もあります。これは、バーベキューの際に、肉や野菜を焼いている周辺に人が集まるような感覚です。作る人と食べる人を分けずに一体となった場で生まれる会話は、とてもリラックスした親しみあるものになります。コミュニケーションするキッチンは、新しいキッチンのあり方を示しています。
また、住宅内でのコミュニケーションは「会話」だけで行うものでもありません。
① 会話によるコミュニケーション
② 表情を読み取るコミュニケーション
③ 気配を感じるコミュニケーション
の3つです。
②の表情を読み取るコミュニケーションは、「家族の帰宅時の喜怒哀楽の表情を読み取ることが可能なリビング階段」について情報提供したり、③の気配を感じるコミュニケーションは、「オープンなリビング・ダイニング・キッチンでは、どこかで誰かが何をしているかが感じ取れるのはもちろん、上下階に於いても何となく気配を感じられる吹抜け」の情報提供をしたりと、徹底的に「お客様のコミュニケーション」を中心とした情報提供です。
まとめ
気づかないうちに変化が進んでいる暮らし方に対応することが、お客様にご納得・ご満足いただいて受注し、暮らしを楽しんでいただく住まいには必須であり、お客様中心の住宅営業と考えます。ご家庭のあり方が多種多様になっている現在、「□□□にするのが一般的」と一般論で情報提供するのではなく、「そのお客様に合った住まいの情報提供」が受注のポイントになります。
《執筆者》
株式会社ハウジングラボ
営業企画課長 眞田 智子









