お客様とのコミュニケーションの主体はビジュアルで
2022/05/05

住宅営業の各場面でのお客様とのコミュニケーションというと、従来は「会話力」が重視されてきました。どうも現在でも営業は「言葉でのコミュニケーション」に重きを置いていますから、「お客様へ耳から情報」をお届けしようとしていることになります。ところが現代社会においてのお客様のコミュニケーション時の情報は、既に視覚情報が80%以上を占めていると言われています。実際にお客様もInstagramのお気に入りの画像をお見せくださって「これが気に入っている住宅のデザイン」とビジュアル情報で伝えてくれています。
自社がそのデザインの住宅が出来る、出来ないは別にして、どういうデザインの住宅がお好きなのかはダイレクトに伝わってきます。これに対して住宅営業が「言葉によるコミュニケーション」で対応していたのでは、情報力でパワーバランスを欠いてお客様に押されてしまっています。今やお客様とのコミュニケーションの主体はビジュアル情報です。
Contents
伝わるコミュニケーション力

最も有効な伝わるコミュニケーション力は、「体感体験」を介しての全身の五感で理解できるコミュニケーションです。特に住宅という内部空間での暮らしは平面図では伝わりませんから、実際に自身が暮らすという視点での「体感体験」に勝るコミュニケーション媒体はありません。
モデル住宅でのお客様が、「ここに住むとしての体感体験」はご自身の暮らしになじむか、という最も大切な部分を判断することも可能になります。「体感体験」は情報が正しく伝わります。モデル住宅がご自身の暮らしに合わなかったとしたらどう修正するのか、合っていたとしても、もっとこうしたいということはあると思います。ここからが営業のコミュニケーション力の真価が問われます。
モデル住宅ではこれ以上の「体感体験」ができない場合の次善の策は、「ビジュアル」な画像を介してのコミュニケーションです。このビジュアルでのコミュニケーションで「伝わる」のは、前提として「体感体験」があるからです。「体感体験」と「ビジュアル」でのコミュニケーションを心がけましょう。
ビジュアルツールの充実を

お客様とのやり取りをどの程度ビジュアル化すればよいのかというと、例えばモデル住宅の案内を「体感体験」を中心として、補足説明はビジュアルな資料で「パッと見たらわかる」ように補足資料を整備します。
「吹抜がある空間が明るい」ということを説明すると、「吹き抜け空間が明るいのは高い位置の開口部からも光がさすので、部屋の奥まで光が届くから明るい」と言葉では「分かったような、分からないような」ことになってしまいます。実際の吹き抜け空間を「体感体験」し、冬至の光の入射角で部屋のどこまで光が入るのかという、A3サイズのイラストを見せられると「瞬時に理解」できます。つまり、モデル住宅の案内カ所のすべてで住宅営業が説明していることをビジュアル化するということです。
●ビジュアル資料をお見せるときの媒体
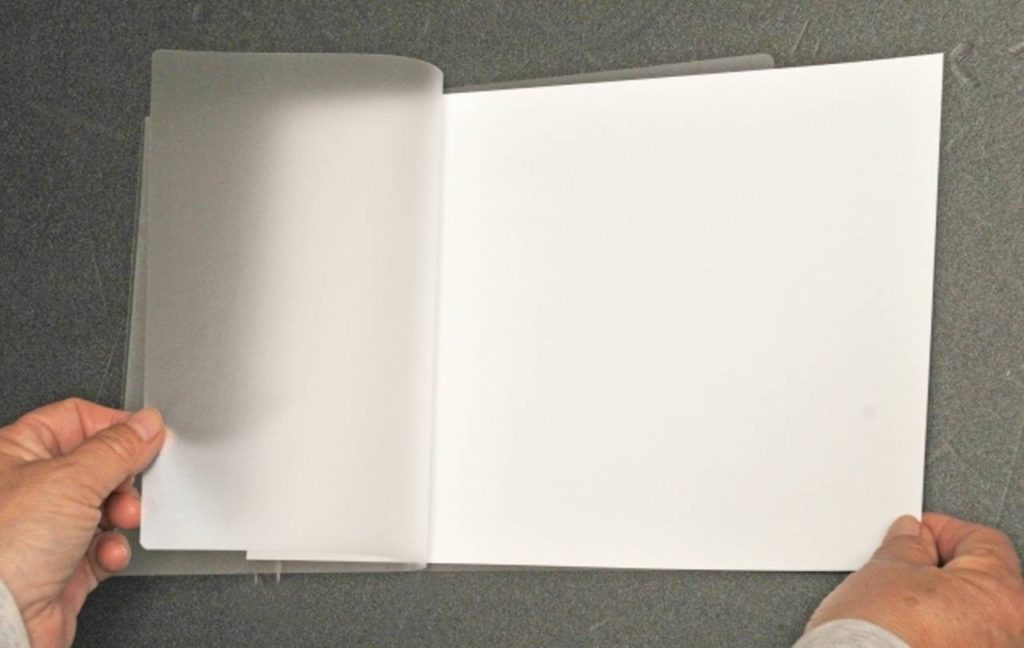


A3サイズのラミネート加工したビジュアル資料か、タブレットでお見せするか、大型モニターでお見せします。大型モニターに接続することが前提なら、スマホのビジュアルなデータでも構いません。
ビジュアル資料には文字は見出し程度に制限して、見たらわかる内容にしますので、ビジュアル資料で「文字を読む」ことは少ないのですが、タブレットでも40才以上のお客様には小さく感じることがありますので、A3サイズのラミネート加工したビジュアル資料か、大型モニターを活用してお見せすることをお勧めします。
インターネット画像検索をフル活用

モデル住宅案内時の自社商品説明には、事前にビジュアル資料を作りこむことも可能ですが、お客様からのご質問や、様々なやり取りの中での対応では、その場その場での適切な「ビジュアル」な説明が必要になります。インターネット上のビジュアル情報を活用します。特にイメージ的なことは「画像検索」で出来るだけ近いイメージの画像を探して共有化します。探すプロセスも含めてタブレットでお見せするか大型モニターでお見せします。
「一緒に画像を探す」ことで住宅営業はお客様と同じ方向を向いて「考える」ことができ、「お客様vs.住宅営業」の関係から「お客様と協力者」の関係へ一段階あがることもできます。最近の画像検索ソフトはよくできていますので、何度か使って想いのビジュアルデータにたどり着くコツを掴んでください。営業スキルの一つです。
モデル住宅以外の営業活動でもビジュアルで情報共有化

時代は「電話」の時代から「Zoom、LINE」の時代です。様々なデータのやり取りができ、「顔を見て」話すことも簡単にできる時代です。「追客中」にもビジュアルデータを有効に使って分かりやすく、お客様と考え方を「パッと見たらわかる」ビジュアルな情報のやり取りで、共有できる営業活動を行ってください。
これは最終的なプラン・プレゼンテーション時も同じですが、節目節目のお客様との確認時には可能な限りビジュアル情報を活用して誤解が生じないようにします。
●デジタルネイティブ世代のお客様が中心

生れたときからインターネットがあった世代(1981年以降に生まれた世代)は、デジタルネイティブ世代で、建築適齢期の世代と言っても良いでしょう。
この年代はスマホに代表されるように、使用に際しての取説などの「言語情報」はないのが当たり前で、こうした面倒なことを好まず直観的に分かるビジュアル情報に慣れ親しんできた世代です。そういう変化への対応も住宅営業にも必要です。
まとめ
建築適齢期の主力年代がデジタルネイティブ世代となった現在、情報のやり取りは今後益々ビジュアル化が加速すると思います。
この潮流に乗り遅れることなく、むしろリードしていくことが望まれます。コミュニケーション媒体の主力が「会話という耳から入る言語情報」から「視覚的なビジュアル情報」へ変化していますので、「上手に話す」ことから「分かりやすく見せる」ことが重要視されてきます。
画像や動画という視覚情報は「こんな感じ」という曖昧なイメージもお客様と共有化することも可能になります。ビジュアルを中心としたコミュニケーション力を高めて行きましょう。
《執筆者》
株式会社ハウジングラボ
代表取締役社長 松尾俊朗
一級建築士












