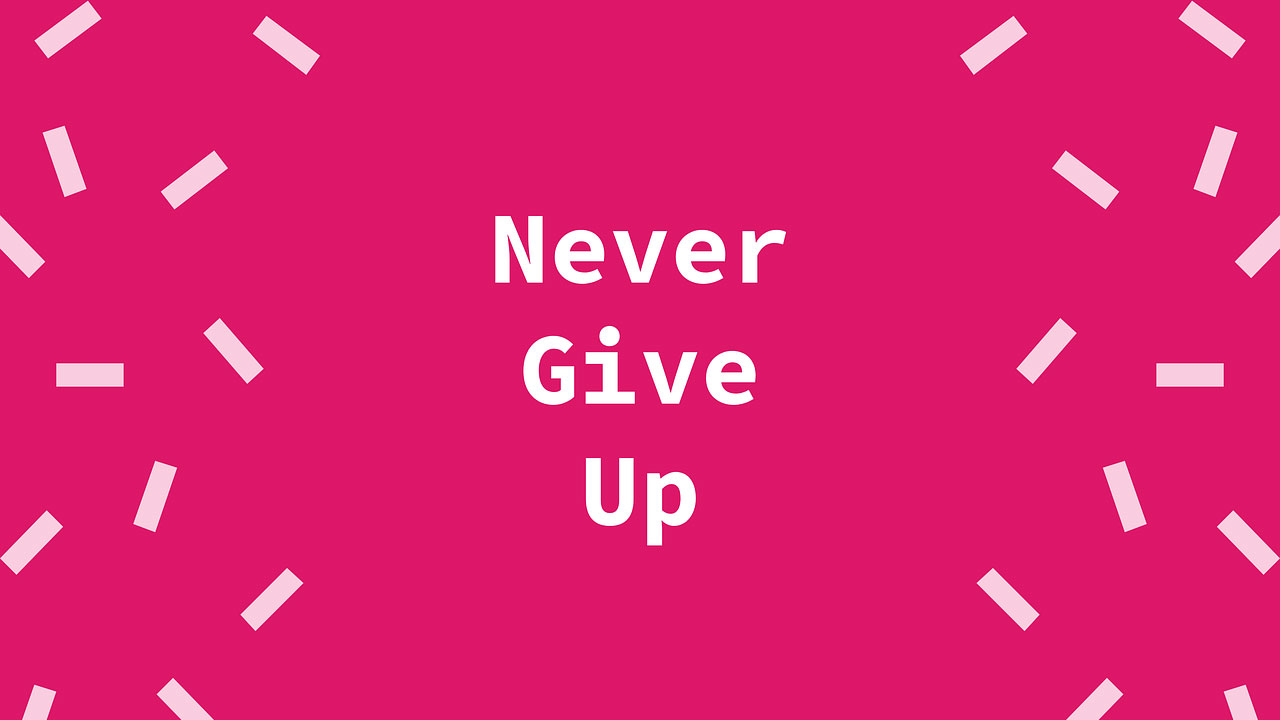フリープランは良い住宅設計なのか考えてみる
2026/01/22

「フリープラン」「自由設計」「何でもできます」ということを標榜する住宅会社を時々見かけますが、これが注文住宅の設計として良い設計をするということなのでしょうか。
これとは真逆で「3000プランから選べます」「特選プラン集」から選んで設計を進めることは注文住宅の設計としては悪いことなのでしょうか。
そもそも注文住宅の設計とはどういう設計が良い設計なのでしょうか。
何に基づく住宅設計なのか

「住宅設計与条件内でお客様の要求をまとめることが設計」ということは一般建築では当たり前のことですが、注文住宅設計には当てはまりません。
「設計与条件内でお客様の要求をまとめることが設計」ということは、言い方を変えれば「設計与条件内でお客様の言いなりに行う設計」ということになります。
注文住宅は、お客様の現在から未来の暮らしにフィットした住空間を設計することです。
お客様は現在からせいぜい5年先までしか見通せていないのが普通です。
30才で家を建ててそこに60年間暮らすという現実をリアルに想像して「お客様はあれこれと要求」を適切にされているのでしょうか。
「注文住宅はお客様の暮らしの容器」とシンプルに考えるとき「お客様はご自身の暮らしを理解されている」ことを前提にすれば「お客様の要求」をまとめることは確かに良い設計です。
問題はほとんどのお客様は「ご自身の暮らしを理解されていない」ということです。
従って「お客様の要求」に従ってプランをまとめることは単なる思いつきの情報も含んでいます。
お客様ご自身の暮らしに置き換えて検討することなくどこかのモデル住宅の「いい感じ」をそのまま「お客様の要求」として鵜呑みにしてしまいこれに基づく設計を進めることは良い住宅設計なのかという疑念が生じます。
設計者は早くプランをまとめたいですから、部屋数と面積、隣り合う部屋などの情報があれば設計できてしまいます。
4LDKで各部屋の広さはどうか、それが総施工面積内に収まっていれば出来上がりという次元で設計が進められているのが実態ではないのかという疑問です。
良い設計とは何に基づく設計なのかという問いです。
お客様の暮らし視点の住宅設計

「注文住宅はお客様の暮らしの容器」ですから、容器の中身の暮らしが理解されていないと注文住宅の良い設計はできないということです。
困ったことに、お客様はご自身の暮らしが見えていませんから「お客様の暮らしという設計根拠」なしに設計を進めることになってしまいます。
それでは暮らしとは何か?
■暮らしを因数分解
1.場
2.コト
3.登場人物
具体的には「リビング(場)」で、夕食後に「ゴロゴロしながらTVでバラエティーを観ていた(コト)」をしていた。
その時「妻はキッチンで後片付け、娘は横でスマホゲーム(登場人物)」というように「場」⇒「コト」⇒「登場人物」で暮らしが立体的に見えてきます。
この現状の暮らしの実態をベースに新しい住まいではどうしたいのか。
例えば、ゴロゴロするのは床が良いのかリクライニングのソファーが良いのか。
飲み物や食べ物はその時何処に置きたいのか、奥様はキッチンから同じバラエティー番組を観れるようにしたいのか、その時奥様の頭上の天井にはスピーカー内臓のダウンライトは必要ないかとか「具体的な新しい住まいで実現したい暮らしのコト」をお客様と共有化するプロセスが必要になってきます。
注文住宅設計業務の最も重要なことは「お客様の暮らし視点の設計」であり、そのために「お客様がご自身の現状の暮らしに気づき、新しい住まいではどう暮らしたいのか」にまず気づいていただき整理していくことです。
●お客様と実現したい暮らしを共有化する
住宅営業部門か住宅設計部門かは別として、住宅設計着手前に「お客様の実現したい暮らしを共有化」して「これに基づく住宅設計をする」ことが注文住宅の良い住宅設計です。
この「お客様の実現したい暮らしを共有化」することが、注文住宅設計の最重要ポイントです。
住宅設計業務を狭い範囲で捉えると「お客様の要求を建築与条件内で図面化」するということになりますが、注文住宅における「良い住宅設計」は、その業務の大半は「お客様の実現したい暮らしを共有化」することが中心になります。
「何度も設計変更を繰り返していつまでもプランが固まらない」、「あれもこれもと要求が増えて面積オーバー/予算オーバーになる」という現象も、この「お客様の実現したい暮らしを共有化」ができていないということが主な原因です。
まとめ
「良い注文住宅設計」というのは「お客様の暮らし視点」で進めることということですが、厄介なことに、この姿が見えない「暮らし」に基づく設計という注文住宅設計は、建築設計のあらゆる分野で最も難しい設計です。
暮らしも「場」⇒「コト」⇒「登場人物」で因数分解すれば、具体的にその姿をお客様と共有化することもできます。
難易度の高い注文住宅設計を担うプライドを持って「良い注文住宅設計」に取り組んでください。
ハウジングラボでは、「お客様が実現したい暮らし」を引き出す「暮らしインタビュー」を進め、住宅建築のプロからの情報提供と合わせて対話を進めていくことにより、「お客様が気づいた実現したい暮らし」を具体化していくための研修を実施しています。
暮らしインタビュー例
https://housing-labo.casa/example/example-6114
研修では具体的なインタビュー手法や便利なツールをご用意していますので、是非お問い合わせください。
お問い合わせ・ご相談(Zoom)申込 – 住宅コンサルティングと研修のハウジングラボwww.housing-labo.com
住宅事業の安定継続/発展に役立つ無料のオンラインセミナーも毎月開催しています。弊社のノウハウの一部を公開していますので是非参加ください。
■住宅事業セミナー
https://www.housing-labo.com/seminar
《執筆者》
株式会社ハウジングラボ
代表取締役社長 松尾俊朗
一級建築士