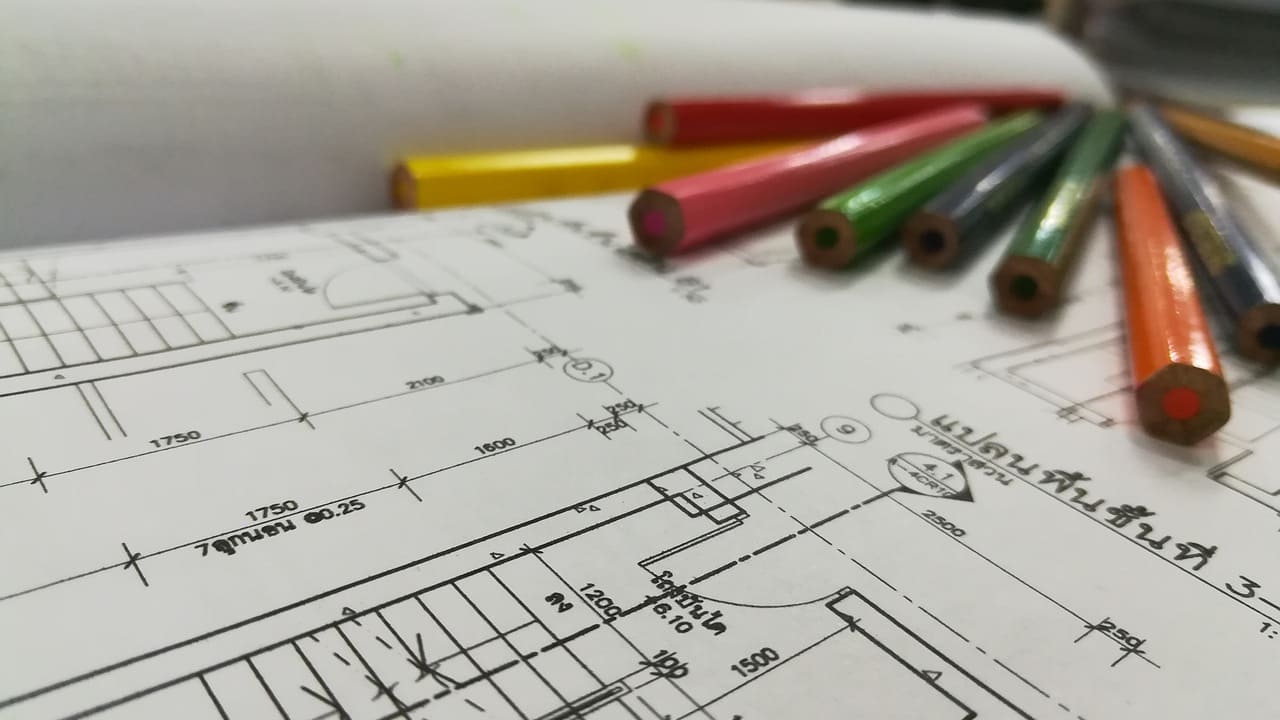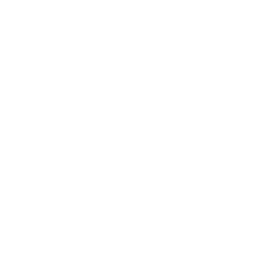注文住宅のお客様との設計打ち合わせはモデル住宅で
2022/04/21

注文住宅の設計は何度も変更があることが当たり前と従来から思われています。何度も変更することでお客様の満足度が上がるという場合もあるかもしれませんが、多くのお客様にとっては面倒な上に、最終的に満足度が低いプランだったという評価が多いのも事実です。時間効率を上げてお客様のご満足度を上げる方法はないかという視点で考えてみましょう。
まず、「設計打ち合わせを行う場所」についてです。
お客様を住宅営業から引き継ぎを受けてから、設計打ち合わせに入ると思いますが、一般に打合せ場所は事務所の打ち合わせ室だと思います。打合せ場所を、可能であればモデル住宅で行うと様々な意味で効果的です。
Contents
図面での打ち合わせでは実際の暮らしを理解できない

3次元空間の住居内の暮らしを、そもそも平面図で理解するというのは、お客様にとってかなり難しいことだと思います。お客様へご提示させていただいたプランと実際にそこでの暮らしについてのお客様の空間認識力のギャップから誤解を生む可能性が高くなりがちです。CGや施工例の画像、もしくは動画などで補正はある程度可能ですが、「体感体験」との差は埋めがたいものがあります。
特にプランヒアリング段階で「言葉」だけの情報に頼ってしまっていると、「とにかく大きなリビング」「もっと大きなリビング」というように10畳でもなく12畳でもなくさらに大きくというような要求になりがちで、住宅全体の面積もオーバーということにつながってしまいます。「お客様が、そのように要求されたのだから仕方がない」ということは通用せず、住宅営業は「予算オーバーでどうするの」と混乱が始まります。
モデル住宅を使って「暮らす」視点で体感体験をしながらの設計打ち合わせ

大きなリビングを求めておられるお客様ご夫婦に、3m、4m、5mと距離を取って普通の声の大きさで話をしていただき、表情がよく見えて、話の内容が詳細まで聴きとれる距離は何処までなのかを確認していただきます。一般には3.6mくらいが無理のない範囲の限度です。3.6m×3.6mの8畳間サイズです。
実際に体感体験していただければ、たちどころに解決する問題です。
リビングを広くという要求内容が実際に大きな面積が必要なことを求めていらっしゃる場合でも、その頻度はどれくらいなのか、ここでは無理なのかと具体的にそこでの使い方をモデル住宅で体感体験しながら考えていただくと、解決の糸口を見いだしお客様と共有化できます。
●「広さ」というのは面積ではなく「広さ感」

お客様との設計打ち合わせで「広さ」についての行き違いは、「言葉による」やり取りが原因である場合が多くみられます。「デジタル数字での畳数、坪数」を言葉にしてしまうとそれが規準となって話が進んでしまいますが、「広さ」は実際の住空間設計では縦方向の広がり、外部への視線の抜けとその場での「広さ感」が本来の基準です。モデル住宅で「広さ感」を生み出している要素を設計が解説して、理解していただきながら打ち合わせを進めると、お客様と円滑に合意できます。
前述のリビングの広さについても、LDK全体空間で感じる「広さ感」で確認していただく必要があります。
●モデル住宅の打ち合わせを効果的するには小道具も大切

キッチンのサイズやテーブルの大きさなどは「カウンター」や「テーブルの天板」を観るだけでは判断がつきません。お皿やホーク、スプーンなどを5セット程度用意して盛り付けの際のキッチンの調理スペース、5人家族の食事のシーンでテーブルの天板サイズはこれで十分なのか、などという体感体験には小道具が必要です。もちろん5m程度のメジャーも長さや、高さ、距離などを測る際に重要にツールです。
小道具の助けをかりながら「暮らし視点での体感体験」が間違いのない判断の共有化につながりプラン変更の削減と、ご入居後のご満足を得ることができます。
プランプレゼンテーションもモデル住宅で実施

設計段階のモデル住宅活用はプレゼンテーション時にも有効です。プランヒアリング時に全ての部位について「体感体験」できていないと思います。また、ヒアリング時に「体感体験」していても印象が薄くなっている場合もあると思います。
プランプレゼンテーション時にもモデル住宅を有効に使って「暮らすという視点で体感体験」で補足しながらプレゼンテーションを進めることは、初回プレゼンでの決定にもつながります。例え初回で決まらない場合も、合意できなかった部位の修正方向を「体感体験」で確実なものにすることができ、「最少の変更回数」に抑えることができます。
お客様とのコミュニケーションは「視覚的な情報」で

コミュニケーションの基本は会話による言葉のやりとりではなく、視覚情報によるやり取りということが鮮明化してきています(80~90%以上)。画像やCG、3D-CADなどで視覚的にお客様とコミュニケーションをとるようにしましょう。「百聞は一見に如かず」の言葉通りです。
●模型やサンプルもコミュニケーションツール

住宅の模型という手に取って確認できるツールは、画面の中だけのCGなどと違って直接的にお客様の感覚に訴えかけること出来ます。また、床材や内装ドアなどの面材他様々なサンプルは、手触り感や表面温度などのぬくもり感と言った触覚からダイレクトに善し悪しが伝わる手段です。時には比較対象のサンプルも使ってこういう家ができるのかというワクワク感も演出することが最終合意への近道です。
まとめ
お客様との設計打ち合わせはモデル住宅で行うことが有効です。土日はモデル住宅も混み合うことが多いことだと思いますので、ゆったりした気持ちで打ち合わせができません。ウィークデーに時間を確保していただき、設計打ち合わせを行っていただくように「お客様メリット」を前面に出して日程調整のお願いしてみてください。案外上手く行くと思います。モデル住宅の活用は営業の場面が主体でしたが、これからは設計もヒアリングに、プレゼンテーションに有効に活用するようにしましょう。
《執筆者》
株式会社ハウジングラボ
代表取締役社長 松尾俊朗
一級建築士