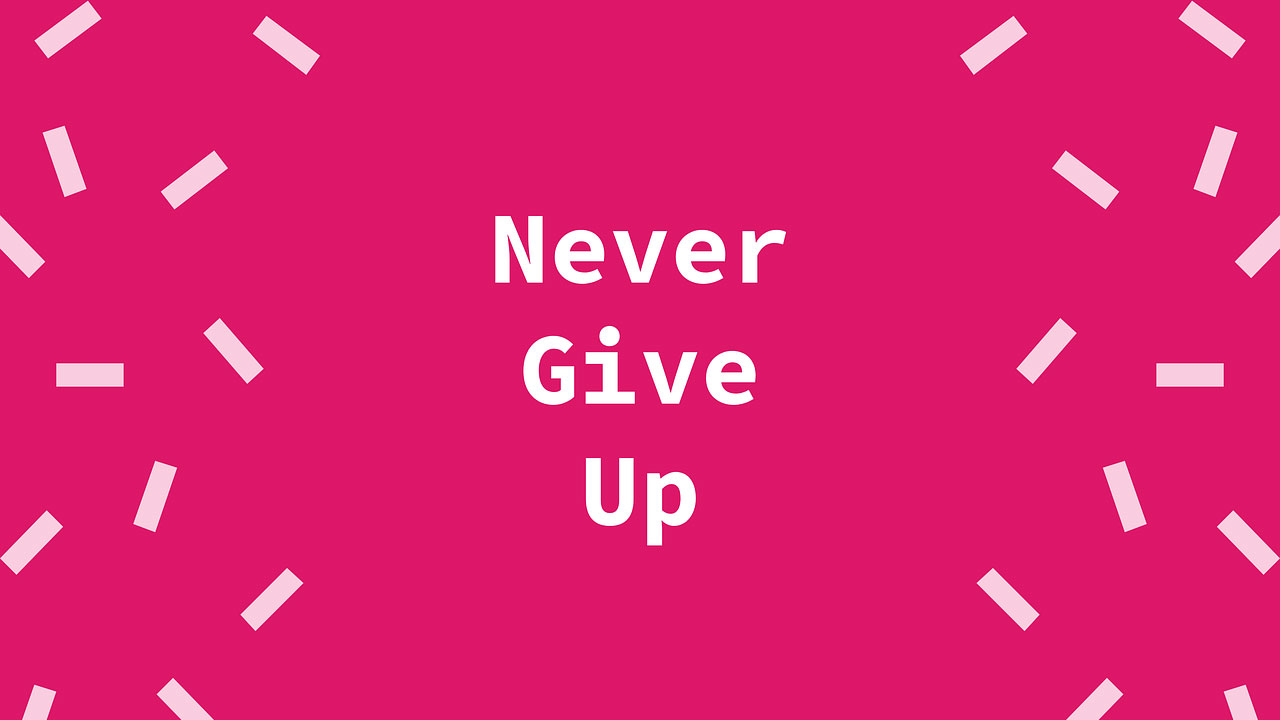住宅設計のデザイナーか間取師か
2022/03/22
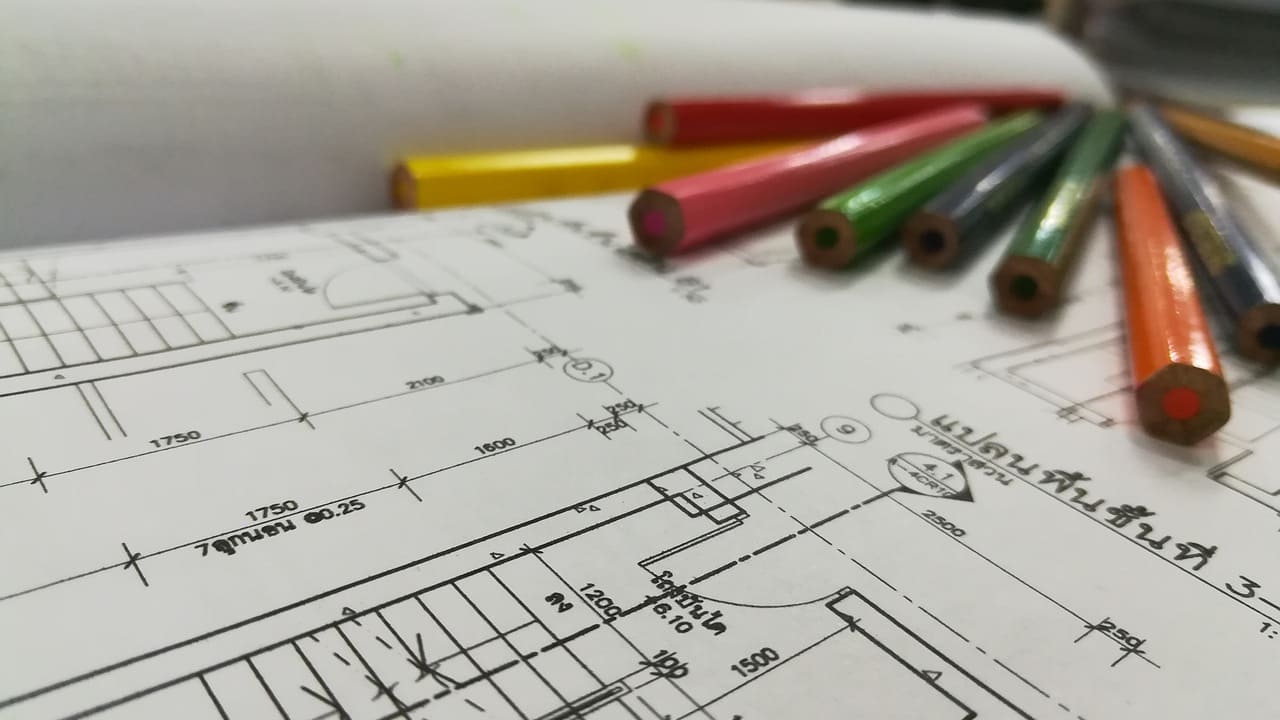
住宅設計者の基本的な「立ち位置」というか「考え方」について記したいと思います。
注文住宅以外の住宅は「建築主」と「使用者」が異なる場合が一般的です。
マンションや建売分譲住宅などがこれに当たりますが、「現物を見て買う」ということからするとジャンルは明らかに異なります。
注文住宅は完成品販売ではなく、白紙から設計する建築物です。
さらに、「建築主」と「使用者」が一致している点が住宅設計難易度を一気に高めています。
ネットの普及が拡大したため主導権はユーザーにあり、年々要求のハードルは上がっています。
これからの住宅設計者はどうあるべきなのでしょうか。
Contents
建築設計者は2分類
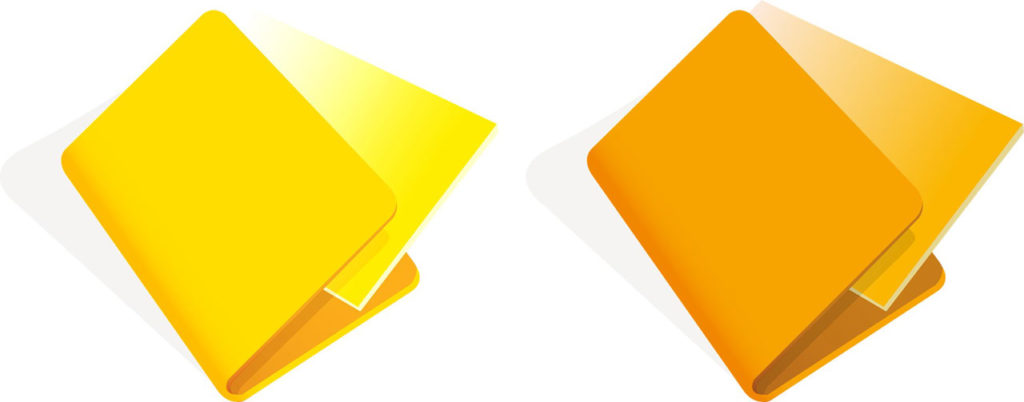
欧米ではARTもARCHITECTUREも同じジャンルで教育を受け、初めてアーティスティックな感覚やデザイン力を学びますが、この段階が終了すると「アーティストの道」か「デザイナーの道」の選択を迫られます。
アーティストは「自己表現者」、デザイナーは「問題解決者」です。
住宅設計者も方向は様々ありますが、住宅会社の設計者は明かに「デザイナー」の方向です。
住宅設計のデザイナーとは
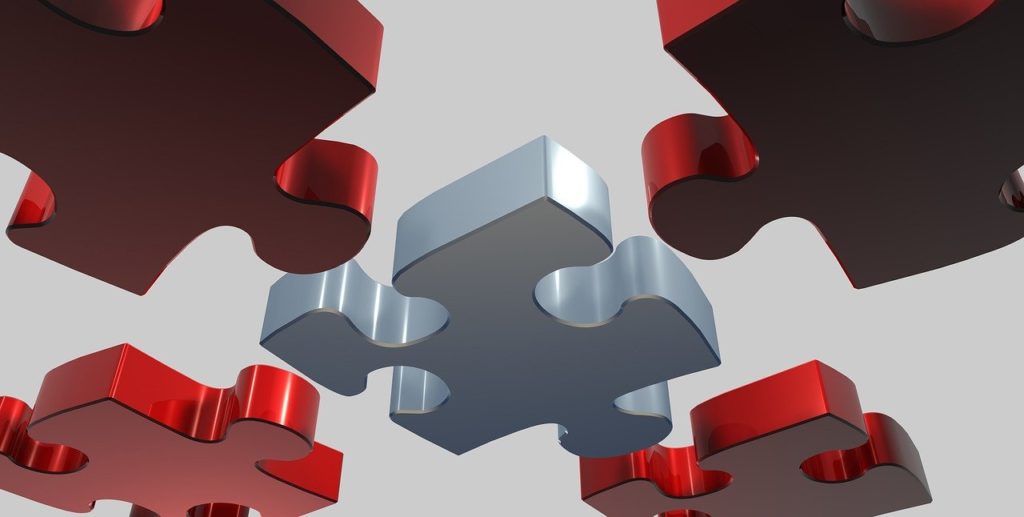
デザイナーが「問題解決者」なら住宅設計のデザイナーは一体どのような問題を解決しているのでしょうか。
限られた敷地面積内で、かつ法的要件をクリアして収める、少ない予算枠内での施主の多くの要求に応えるなど、難題が突き付けられる場面は多々あり、これを日夜解決しているのだと思います。
全ての建築物の設計で、こうした「問題」と設計者は格闘していると思います。
ただし、注文住宅となると「要求された問題を解決」しているだけでは「間取師」であって、お客様の暮らしを中心に考えて、より心豊かな暮らしを実現するという「本来の注文住宅設計の問題解決」に至っていません。
ここに気づくかどうかが住宅設計のデザイナーのレベルを決めます。
●要求と条件に縛られるな

建築資材の価格が上昇してくると益々予算内に収めるという設計の難易度は上がります。
確かにそういう「与条件」は顕在化していますが、この条件の根拠は正しいのでしょうか。
「住宅営業から予算はオール込みで3000万円と言われた」、「リビングは20畳、和室は10畳・・・」というような情報はどのような根拠があるのでしょうか。
一般建築物の場合には、こういうことはあまり考える必要はありませんが、注文住宅の場合はそうはいきません。
情報を鵜のみにして、それに縛られて「問題解決」しても、多くの場合、お客様は不満を抱き何度も設計変更が生じています。
本当の意味での「問題解決」がなされていないということです。
情報の根拠、要求の根源に遡って問題を理解する必要があります。
●住宅営業担当者との協力で設計根拠になる情報を掴む

「リビング20畳は何をするために必要なのか」が知りたいのですが、お客様に理由を問いただすという質問攻めでは、お客様を追い詰めるだけで、気分を害され心が離れてしまします。
「お客様の暮らしを中心に考える」という、お客様の側に立って住宅設計者が一緒に考えるスタンスをとると、住宅営業担当者だけでは成し得なかった設計根拠にたどり着けます。
この延長線上の考え方で「予算枠」を大きく拡大することも可能です。
「こんな暮らしがしたかった」という気づきをお客様と共有化してご一緒に考えます。
実現したいコトが明確になれば「単なる消費」から楽しい暮らしという「時間の質を高める投資」に考え方が変わり、予算枠が拡大します。
お客様と設計者はモデル住宅での打ち合わせが基本

要求された部屋数等を建築条件内に押し込んでまとめ上げるという「間取師」の仕事なら、デスクワークで十分です。
単なる「住宅を買うという消費視点」から「住まいを楽しみ人生を楽しむ暮らしの実現」という「人生への投資視点」という発想になると、「リビングで家族で楽しみたいコト」、「同じ場所でそれぞれが別のことをしていても楽しい空間とは?」と考えると、お客様にモデル住宅を活用して体感体験していただきながら考える必要があります。
平日、休日の過ごし方を具体的にモデル住宅で暮らすとしてという視点で、未来の暮らしを組み立てて行きます。
【参考記事】住宅設計の打ち合せは、1/100の図面より実物空間の方が効果大
●実現したいコトの共有化

暮らしのシーン別に、実現したいコトの具体的な内容を共有化しながら重視するポイントの強弱をつけて暮らしの重心を見いだしていきます。
優先順位付けというよりも、これだけはぜひ実現しましょうという暮らしの重心の発見と共有化です。
注文住宅設計のデザイナーの能力としては、部屋数が足りないとか収納が足りないといった暮らしのマイナス要素を解決していくだけだは不充分です。
家が新しくなるならこれらのことは解決されて当たり前で、それだけなら安い方が良いとなってしまい価格競争に陥ります。
●住まいを楽しみ人生を楽しむ暮らしを描けてこそのデザイナー

暮らしの重点ポイントとその中でも最も重要な暮らしの重心を共有化できて、初めて本来の意味での注文住宅の設計上の「問題解決」ができたと言えるでしょう。
お客様の生涯の幸せを願うという設計者の眼差しが、注文住宅設計デザイナーの考え方の源泉です。
設計与条件内で間取のパズルを解くという「間取師」から、本来の注文住宅設計デザイナーの道へ進みましょう。
まとめ
耐震性能に有利なプラン、断熱機密性能を活かすプランなど従来にはなかった設計への「要求要素」も加わって、より複雑な条件の中で進める注文住宅設計の難易度が高くなってきています。
しかしそれは前提条件であって、本来の「住まいを楽しみ人生を楽しむ暮らしの実現」という住宅設計者に求められる命題は、よりお客様の価値観や実現したいコトという暮らし視点が求められています。
個の生活が多様化した現在では、「間取師」から「住宅設計デザイナー」へ進化することが社会的にも求められています。
前進しましょう。
《執筆者》
株式会社ハウジングラボ
代表取締役社長 松尾俊朗
一級建築士