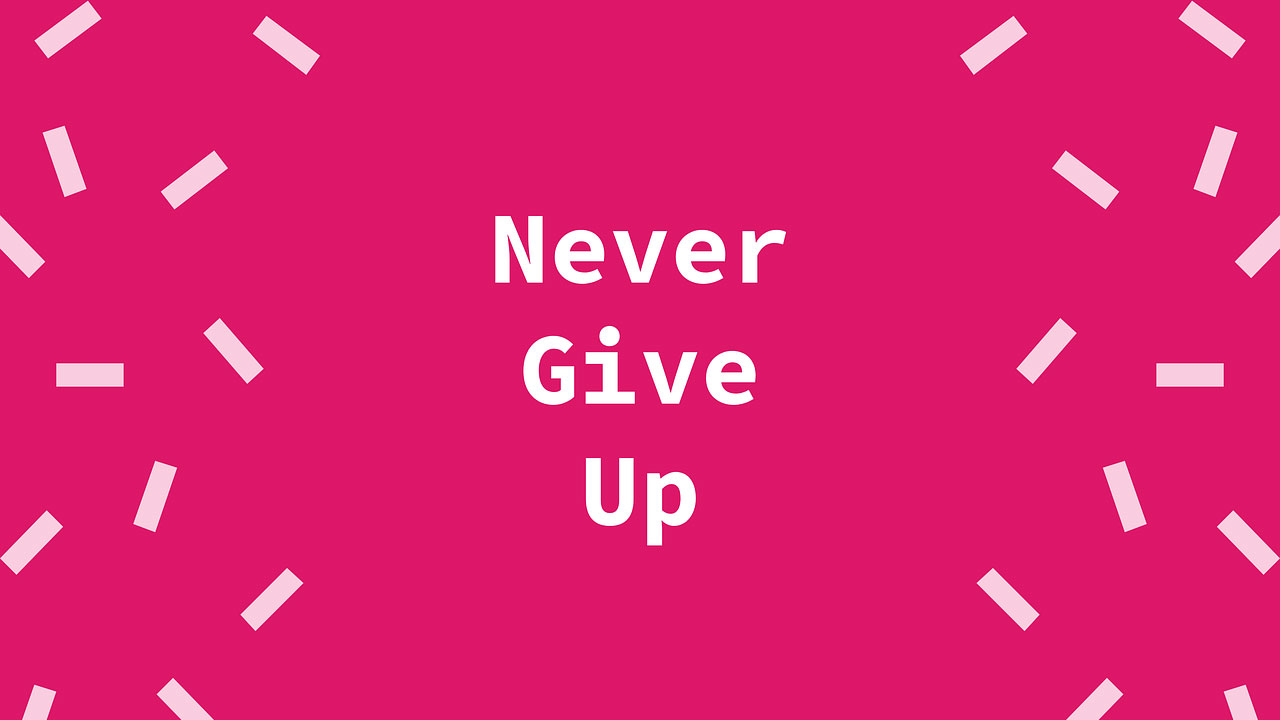時代を超えて資産になる住宅とは
2022/03/27

夏は高温多湿で、冬は寒く、台風も、豪雪も、地震もあるという災害大国日本で、100年とかいう単位ではなく、時代を超えて数百年後も資産になる住宅というものは本当に作れるのでしょうか。
おそらくハード的に考えれば、現代のテクノロジーでおそらく実現可能なのでしょう。
相当金額的には高くなりそうですが、ある程度の現実的なコスト内で可能なのかもしれません。
しかし、そもそもそうした住宅は果たして必要なことなのでしょうか。
Contents
竪穴式住居は13000年のロングライフ住宅

日本の住居の歴史を振り返ると、自然への畏敬の念が強く、自然を克服してやろうなどと大それたことを考える人たちは少数派で、「自然と上手く呼吸を合わせて行きましょう」的な考え方が強いようです。
また、どうせ台風が来たら飛ばされるのだからと竪穴式住居という簡易型住居が13000年間も続いたように、軽妙なScrap and buildを基本にしているようです。
名建築として残っている住宅

地域の暮らしと密接にかかわりながら、文化財的価値がある住居は確かに残っています。
新潟の豪農の家、白川郷の住居群、京町屋、元祖家族のための住宅として保存されている「聴竹居」など、様々な角度から次々と具体例は上げられます。
中には現役バリバリの住居もあります。
文化財的住居は観光資源として見なされていますし、新しい視点でリノベーションされて様々な用途に活かされている住居もあります。
それは建築物自体が文化的な資産に昇華した場合で、住居が住居のまま現役を貫いているのかというとやや怪しくなってきます。
文化財と住居は異なりますから、「快適に住まう」と考えて、なおかつ文化財としての価値を損なわないとなると、相当な「根性と資金」が必要になってきます。
住宅として快適に住まうのであれば当事者としてはやはりScrap and buildと考えてしまうのが現実のようです。
●海外の時代を超えて資産になっている住宅

オランダのアムステルダムの不動産屋さんの前を通ると「17C」とか「18C」という暗号のようなものが書かれいている「物件案内」を目にします。
17Cは17世紀に建築されたという表記で、「古ければ古いほど良い」のだそうです。
「あのう、そこの17Cの建物傾いて隣の建物に寄りかかってますけど・・」というのは愚問らしく、「実績主義」で「350年も使われて来た実績があるんだからそれがどうした」だそうです。
石造かレンガ造のメーソンリー(組積)造で、確かに地震も台風もない地域ではそうした評価なのでしょう。
「350年間ずっと住宅として使われてきたんだ」と思ったら、「いや、いろいろだよ。住宅として建設されたが砲弾倉庫にもなっていたし、最近まではコンビニ、去年から住宅にまた戻ったね。100年振りに。」だそうです。
この多用途性があるから生き残ってきた「住居」で、その時代に合った使い方をされてきたようです。
確かに「住居としても使える」が、建築物として「資産価値」があるようです。
●時代を超えられるモジュール

オランダの「17Cの住居」の平面モジュールは6m×4m、外にも様々なモジュールがあるようですが、いずれも大スパンです。
また、高さ、方向も階高5mもあったりします。
20世紀の巨匠ミース・ファン・デル・ローエ設計のシカゴにある高層マンション事始めのレーク・ショア・ドライブ・アパートメントにも同じようなことが言えますが、水平方向のモジュールは様々な用途や暮らし方に応じて改装可能です。
高さ、方向のゆとりは近代化で、様々な設備配管が増えても天井フトコロが大きく、許容してきたようです。
時代を超える住宅を生むためには、縦横高さのモジュールの大きさが、次の時代を許容する条件でしょう。
●「時代を見通せないから生まれた」大きなモジュール

ミースはナチスから逃れてアメリカに亡命する前に、バウハウスの第3代校長を務めていました。
同僚に抽象画の開祖カンディンスキーやクレーという従来の価値観を破壊するような鬼才が多く、「20世紀後半から先の時代は見通せない」から「何が起こっても許容できる建物」を原則と考えた節があります。
ミースの言葉であまりにも有名なLess is moreというのも、その一環の考え方かもしれません。
ミースの代表作の一つのイリノイ工科大学のクラウンホールは、四周ガラス張りの高天井の巨大なワンルームです。
「時代の先を読むな、許容しろ」というのが時代を超える条件かもしれません。
●もっとシンプルに考える住宅が必要なのかも

あらゆる時代の、あらゆる暮らし方を許容し、簡単な改装でその時代を楽しめる住宅。
余計なことは全てそぎ落とし、それこそLess is moreで考えると、住宅は空っぽのハコになってしまいます。
敷地の建ぺい率・容積率限度一杯で斜線をかわした可能な限りの大きな箱を作り、建ぺい率や容積率が時代で変化したら足せるような美しい箱ということになってしまいます。
シンプルな回答ですが、実現は難しいというのがどうも現実のようです。
まとめ
住宅のあるべき姿を考えるという視点は、本来住宅事業に関わるプロなら当然ですが、中々そういう機会はありません。
今回のこの記事(というか筆者の妄想)が皆様のプロとしての知的な刺激になれば幸いです。
時代を超えて資産となる住宅とは、数世代、十数世代以上にも亘って受け継がれる住宅ですから、個人資産ではなく社会資産としての住宅です。
長い時間軸を下敷きに現実の商品開発、個々のお客様への住宅づくりと真摯に向き合っていきたいと思います。
《執筆者》
株式会社ハウジングラボ
代表取締役社長 松尾俊朗
一級建築士