工務店・住宅会社・ホームビルダーの「考える住宅営業」の人材育成
2022/03/03
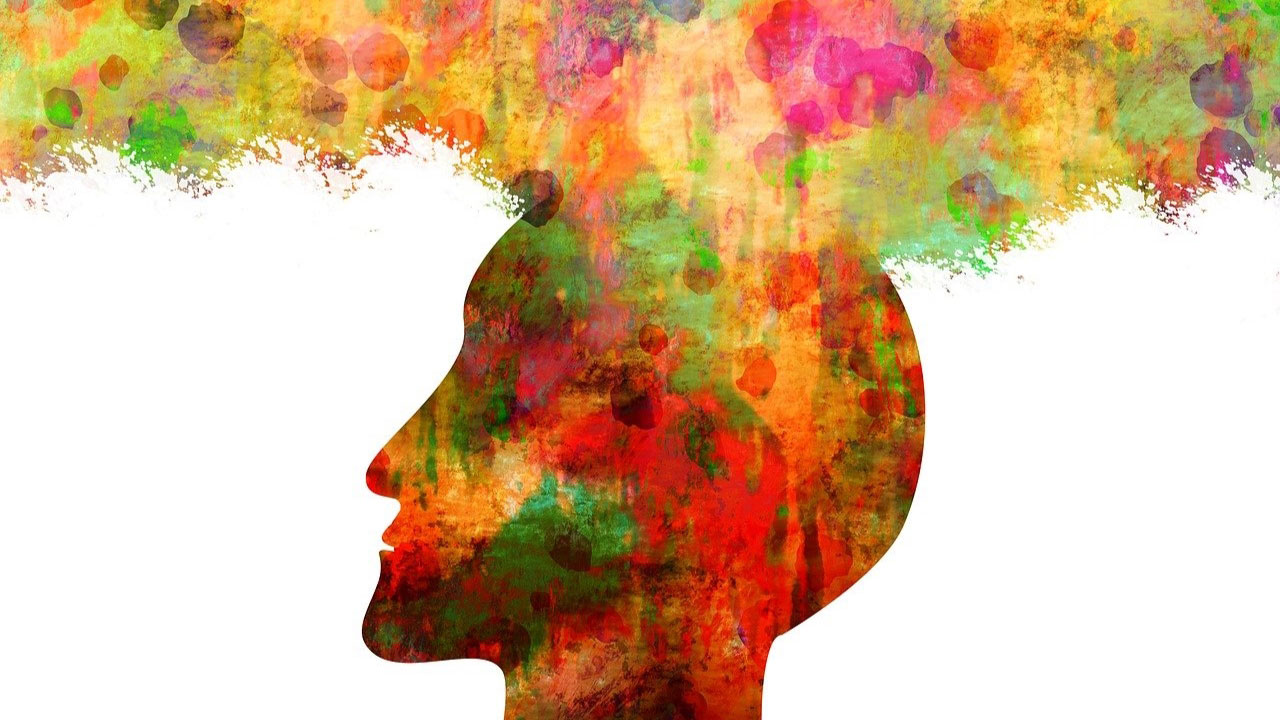
「教えることが教育」という考え方が根強く残っていますが、「教えたことしかできない」と嘆いている実務前線の長の声をよく耳にします。
17世紀のフランスの思想家パスカルによると「人間は考える葦である」のだそうです。
つまり「考える」ことに人間としての価値があるということです。
教えたことをやらせるならAIとロボットで十分間に合うような時代です。
お客様と向き合い、課題と向き合った際に「考える人材を育成」しましょう。
新人や部下を考える人材に育成するにはどのような指導が適切なのか、住宅営業という職種で考えて行きましょう。
Contents
「考える」目的は何か
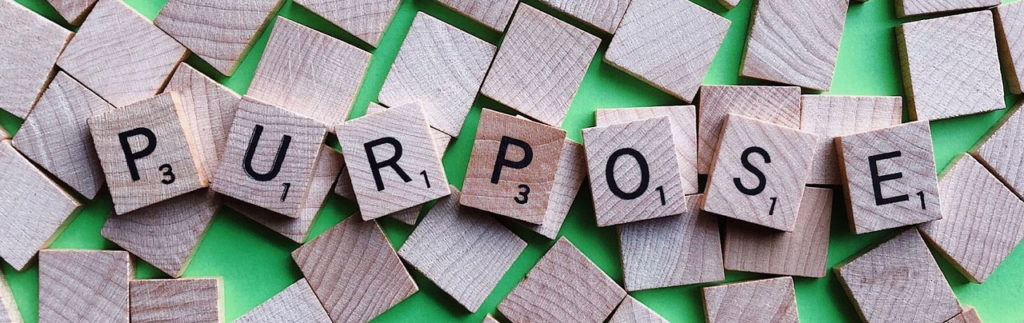
「考えろ」と言ってもなにをどう考えるのか分かっていない状態で「考えろ」と言われるのはさすがに酷です。
パワハラで訴えられかねません。
先ず考える「目的」です。
「お客様の住宅を受注するために考えろ」でしょうか。
「受注する」というのは「目標」であって「目的」ではありません。
営業の目的は「住まいを楽しみ人生を楽しむ暮らしの実現」というような住宅受注をすることで、お客様にどういうメリットを提供するのかという本質的な目的ことです。
「仕事をする具体的な目的と本質の明示」です。
「目的」無き「目標」数字をただ追いかけろというのは長くは続きませんが、「お客様を幸せにする」というような「仕事の目的」を明確に社内で共有化できれば「目的」を達成するために「考える」ことができます。
お客様の暮らしを中心に考える

注文住宅営業の目的が、仮にお客様の「住まいを楽しみ人生を楽しむ暮らしの実現」とするのであれば、お客様にとって住まうことで何を楽しみたいのか、家族で一緒に料理を作ることなのか、人生の楽しみは何なのかというお客様の価値観やお考えに基づく新しい住まいで実現したいコトをお客様中心に考えます。
この実現したいコトというのは「聞けば答えてくれる」ようなものではなく、お客様も気づいていない内容です。
モデル住宅などでの体感体験を通して暮らしへの触発が必要です。
●住まいづくりの目的の共有化
「とりあえず家を新しくしたい」、「暖かい家が欲しい」、「収納たっぷりの家にしたい」と、一般にお客様はこのような根拠で住まいづくりを始められますが、「新しい家では今後の人生の70%の時間を過ごす」という事実も未確認のままです。
「いい箱が欲しい」のではなく「いい暮らしがしたい」はずですが、スタート時点ではどうも話が短絡しているようです。
「お客様へこれからの暮らしで実現したいコトを触発」して「その反応をキャッチする」ことで「お客様の住まいづくりの目的をご一緒に考える」ところから始まります。
●実現したいコトの明確化
「夫婦で仲良く暮らしたい」、「ペットを飼いたい」というような漠然とした内容や小さな幸せなどの「実現したいコト」を具体的にしていくことです。
どうすれば実現できるのか。
どのレベルで実現したいのかお客様と一緒に考えます。
この場合の「考える」という行動は、「具体化」のプロセスを進めるということです。
まず画像で「こんな感じ」というイメージを共有化して、次に実現したい状態に近い空間を何処でどのように体感体験していただければ伝わるのかを「考える」ことです。
本質と目的で考えること

お客様の住まいづくりの「目的」が「住まいを楽しみ人生を楽しむ暮らしの実現」であり、これが住宅事業を進めている自社の注文住宅事業の「本質」の考え方と一致しているなら、考え方の軸はブレることはありません。
この目的と本質で考えるということを実際の案件で受注活動に置き換えて具体策で考えて行くこと自体が、考えることができる人材育成です。
●対処療法ではなく本質対応
「ここにこんな収納が欲しい」とおっしゃるお客様へ、ハイハイと対応することは「考える」ことを放棄しています。
「なぜそこに収納が欲しいとおしゃっているのか」を考えることです。
常に「本質」で対応するためにはどうすればよいのかと「考える」ことです。
●お客様に生涯心豊かに暮らしていただく
考え方の基準は「お客様の幸せ」という「ユーザーメリット」です。
お客様の建築与条件の範囲内で、最大の満足をいただくためにどうすればよいのかを考えることが営業の仕事であると認識することで、「考える」力がついてきます。
指導者は手取り足取りではなく、例えば「一緒に考える」伴走者の位置に立つ必要があります。
また、「考えとけよ」の放置でも「過保護」、「オーバーティーチング」でもない、実務実態を把握しての適切なアドバイスをする「コーチング」で考える人材を育てるということです。
まとめ
「考える」人材は特に営業に求められます。
多くの職種がやがてAIに置き換わっても、注文住宅営業だけは人の暮らしを中心に考えるビジネスですから、住まいづくりの「目的と本質」で「考える」人材が最大の武器になります。
実務責任者が実務の中で「コーチング」などの指導方法を身に着けて人材育成に当たることも重要なポイントです。
自社の中だけではなく専門の指導を受けることもおすすめします。
《執筆者》
株式会社ハウジングラボ
代表取締役社長 松尾俊朗
一級建築士









