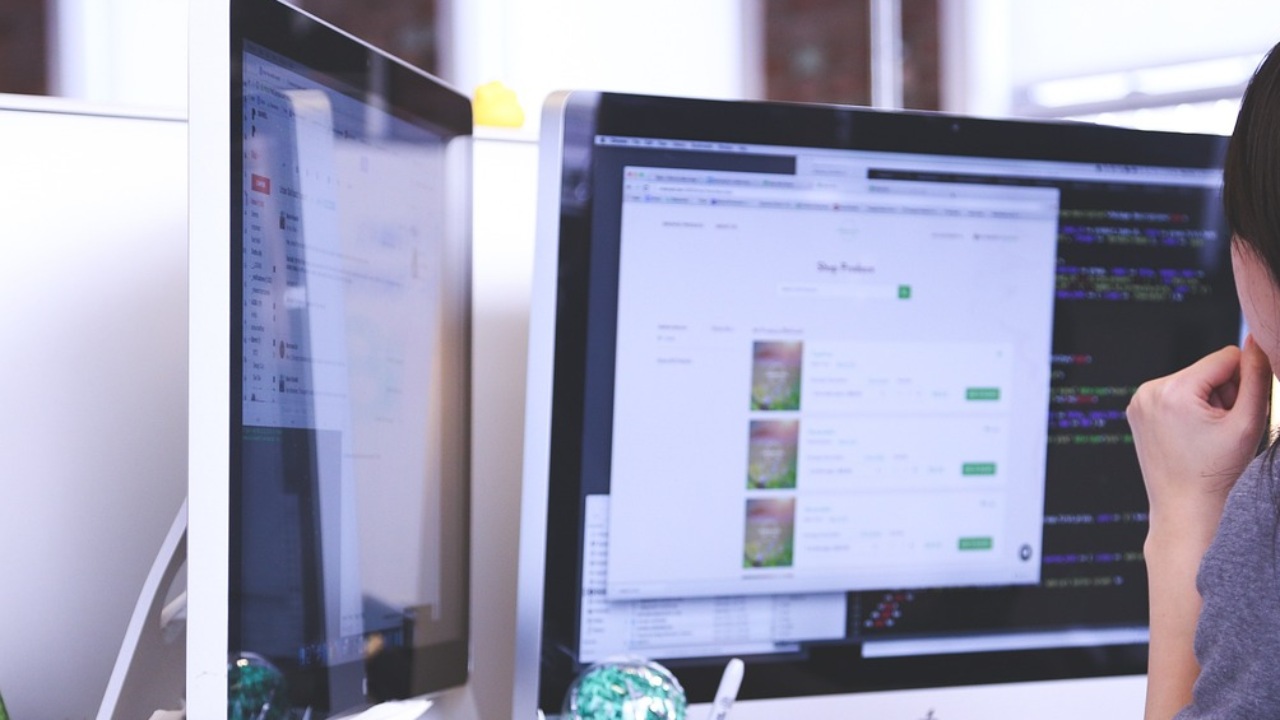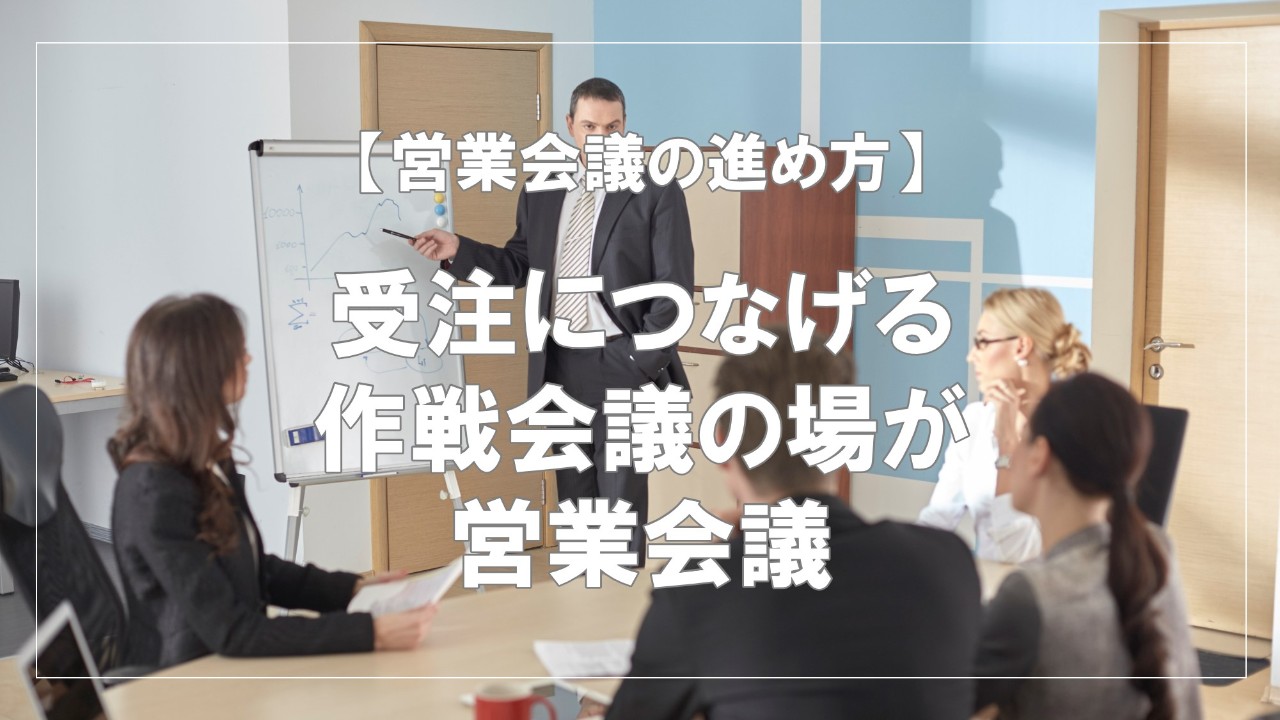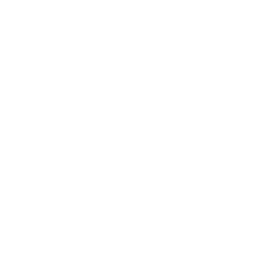注文住宅業界の競合分析の方法
2023/10/13

受注を獲得するためには、必ずと言っていいほど存在する同業他社のことを知ることは欠かせません。
しかし、意外と同業他社のことを正しく把握している住宅会社・工務店は少ないものです。
今回は、競合分析を行うための方法について考えてみます。
Contents
競合分析とは

競合分析とは、自社商圏内で競合する住宅会社・工務店の強みや弱みなどの特徴を調べて、どのようにしたら自社が優位になるのか、受注戦略を改善していくことに活用することです。
競合他社との比較だけでは受注につながらない
同業他社の情報を収集して比較した結果、「A社は自社よりも断熱性能が低いから、断熱性能の優位性を訴求していく」という戦略をとる住宅営業担当者がいらっしゃると思います。
この戦略も一つの視点ではありますが、他の視点も加えて比較し、自社と他社の違いや自社の強みを明確にして、その点の優位性を訴求していく方が、より受注に近づく戦略をとることができます。
住宅営業が知っておくべき競合他社の項目

まずは、受注を獲得するために他社がどんな商品を売っているのか、どんな理念の会社なのかを知っておきます。
【外観】
商品ラインナップごとに、和風なのか洋風なのか、どんなテイストなのかなどの外観の特徴を把握します。
家の印象を決定づける外観デザインのバリエーションの把握です。
【プラン・空間】
どんなプラン・空間づくりをしているのか、特徴を把握します。
【構造・工法(性能)】
構造、断熱性能、耐久性能などについて等級以外にも、どのような部材を使用して、どのような特徴があるのかも把握します。
【仕様(設備・部材)】
換気システム、サッシに代表されるような、住宅に使用している設備部材を把握します。
【暮らしやすさ】
お客様の暮らしやすさを考えた住まいづくりの考え方を把握します。
【住まいづくりプロセス】
住まいづくりの流れ、保証内容、アフターサービスなどについて把握します。
【価格】
商品ごとの価格や価格に対する取り組みなどを把握します。
【住まいづくり】
住まいづくりの考え方(ポリシー)を把握します。
同業他社との違いを把握する

上述した8項目「外観」、「プラン・空間」、「構造・工法(性能)」、「仕様(設備・部材)」、「暮らしやすさ」、「住まいづくりプロセス」、「価格」、「住まいづくり」の自社バージョンも明確にします。
そのうえで、他社との違いは何か、自社の強み、弱みは何かを正確に把握して、競合時の戦略に役立てます。
他社との違いを受注戦略に組み込む
住宅業界において、お客様の購入判断基準は「暮らしをより楽しくしてくれるコト」です。
モノの優位性の訴求では差別化が難しい
「モノ」が充足した日本では、「モノの違い」よりも「モノによって得られる幸福感」での差別化が効きます。
例えば、温熱環境が自社の強みの場合、「断熱性能等級5なので、夏涼しく冬暖かい」と訴求するよりも、「冬でも裸足で」などの訴求の方が、お客様にはスッと実感でき、わかりやすい説明です。
冬でもTシャツに短パンで過ごせる家なのか、セーターとフリースを着ても寒い家なのかなどの、暮らしにどんな変化があるのかという説明です。
お客様を知る
お客様が比較している競合他社の何を気に入っているのか、何を不安に思っているのかなどの「想い」を知り、この「想い」に適した自社住宅の優位性を訴求します。
お客様に不快感・不安を与える説明はダメ
お客様から、比較検討している競合他社のことをお聞きした後に、その会社もしくは住宅商品の弱みを貶める説明は、お客様を不快にさせますので、「他社をリスペクトした上で自社の良いところを伝える」方法をおすすめします。
まとめ
お客様が比較検討する住宅会社・工務店が必ずと言っていいほど存在する現在、他社の情報を把握して差別化を図るというのは、受注を獲得するためには必要な対策です。
自社住宅商品の客観的な把握、他社情報に加え、お客様の想いを知り、これに応えるることが受注への最重要ポイントです。
ハウジングラボでは、お客様の「納得」と「満足」を高めて標準6週間で受注を獲得する住宅営業手法をご用意しています。
自社特徴の好印象化で「いいね」を積み重ねる「インプレッション(Impression)営業」、自社目玉特徴を刷り込み好感度の核をつくる「インプリント(Inprinting)営業」、お客様が実現したい暮らしに気づく「触発/気づき(Inspire)共感営業」の3つの住宅営業手法をもとに、住宅事業の安定経営をサポートします。
「商品」「商品開発」「集客・マーケティング」「営業」「設計」「マネージメント」の5分野からなる住宅営業サポートです。
是非ご活用ください。
■ハウジングラボの住宅営業サポート
https://www.housing-labo.com/consulting
住宅事業の安定継続/発展に役立つセミナーも開催しています。
■住宅営業セミナー
https://www.housing-labo.com/seminar
ハウジングラボの3つの営業手法の説明会です。
■「顧客心理を捉えて、価格アップでも受注出来る3つの住宅営業手法」説明会
https://www.housing-labo.com/form_content/form_content-4723
《執筆者》
株式会社ハウジングラボ
営業企画課長 眞田 智子