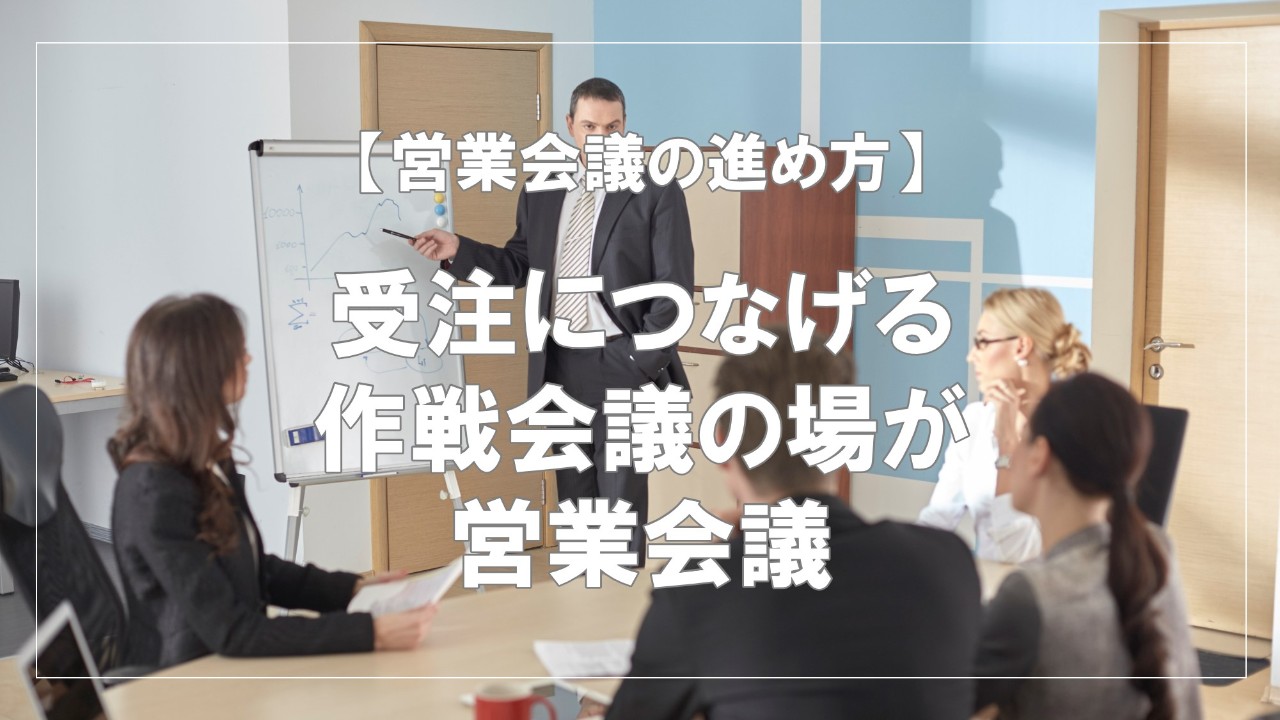競合他社とは異なる差別化戦略で受注する
2023/03/24

「モノ」としての住宅が売れていた時代には、住宅の構造・性能などのハード面の優位性を訴求することが受注に有効でした。実際に、持ち家着工数は1973年をピークに多少の上下はあっても下降傾向です。さらに、1978~1982年を境に、何かを購入する際の判断基準が、「モノの豊かさ」より「心の豊かさ」を求める割合が逆転しています。今回は、ほとんどの工務店・住宅会社がまだ導入していない「心の豊かさ」で差別化して受注する住宅営業について考えてみます。
Contents
差別化戦略とは

「差別化戦略」とは、競合他社とは異なる、もしくは、競合他社には無い自社住宅商品の特徴や強みで優位性を持つことです。
「モノ」が売れた時代の住宅営業
戦後の昭和20年代の初め頃に日本で住宅が不足し、昭和30~40年代にかけての高度経済成長期に合わせて「いつかはマイホーム」という人生の目標が大きく捉えられていた時代には、住宅が不足していた環境も相まって「モノとしての住宅」で充分に売れていました。そして、バブル経済の崩壊や阪神淡路大震災の影響で財布の紐が固くなったお客様に住宅を売るために、「モノ」の差別化として「安心安全の家」や「健康に良い家」などの訴求で差別化を図ってきました。そして、現在もこの訴求での差別化が根強く残っています。
今まで通りの住宅営業方法では差別化が難しい
現在の日本では、「モノ」は充足し、さらには、マンション(分譲・賃貸)、貸家など、所有しなくても居住する住居形態も様々あり、「持ち家」にはこだわらない方も増えています。さらに、先述した通り、購入する際の判断基準が「モノの違い」よりも「モノによって得られる幸福感」に変化しています。このように変化した「住居に対する考え方」や「購入の判断基準」を放っておき、従来通りの営業だから、という理由で、「モノ」の違いを訴求する営業を続けて良いのでしょうか。
耐震性に優れ、温熱環境も整い、空気環境も良し、などの訴求をされている多くの工務店・住宅会社のホームページが存在します。そして、住宅営業担当者は、この「耐震性」、「温熱環境」、「空気環境」こそが、自社の強みであり特徴であると、お客様に一生懸命説明されています。しかしながら、お客様はご来場前にホームページやSNSで事前に各工務店・住宅会社の情報収集と検討を行っているため、各社の住宅性能を目にしています。お客様は住宅のプロではありませんから、「性能等級の差や構造に多少の違いはあっても基準を満たしているなら問題無し」という認識です。そのため、住宅の性能は、もはや特徴ではなくあたり前という感覚になっています。
住宅の性能だけでは差別化が難しいのです。
これからの差別化戦略

住宅業界において、お客様の購入判断基準は「暮らしをより楽しくしてくれるコト」です。
暮らしのワンシーンで「楽しいコト」を触発する
例えば、ワイン好きのご夫婦に対して、市販のワインセラーではなく温度・湿度・紫外線をコントロールできる専用ルームを提案する必要はありません。ワインを、いつ、どこで、誰と、何をしながら飲むのかをお聴きし、このワインを飲むシーンをどのような空間で、どのように飲みたいのかを確認します。
リビングのソファーとローテーブルで、ゆったり夫婦で会話しながら飲みたいのか、落ち着いたワインバーのような雰囲気のカウンターで一人ゆっくり飲みたいのか、など数パターンのワインの飲みかたのシーンをお伝えします。このお伝えしたシーンが起爆剤となり、お客様は「自分だったら・・・」と考えてお話しくださいます。これが触発です。そして、お客様がおっしゃったワインを飲むシーンを実現するための情報提供が受注につなげるための大切なポイントです。
空間イメージを共有する
言葉でのやりとりでは、イメージの食い違いが生ずる可能性が高いものです。
例えば、「オシャレなカウンターで一人でワインを飲みたい」お客様には、「オシャレ」のイメージを共有する必要があります。「オシャレ」といっても感じ方は人それぞれですので、ネットで画像検索して、どのカウンターがイメージに近いのかを共有することをおすすめします。
まとめ
多くの工務店・住宅会社が実施している「モノ」としての住宅の性能での差別化が難しい現在、お客様の楽しい暮らしを基点にした住宅営業は、導入している会社が少なく、さらに「コト」が判断基準になっているお客様に差別化して受注する大きなポイントですので、是非、「コト営業」をお試しください。
ハウジングラボでは、お客様の「納得」と「満足」を高めて最短6週間で受注を獲得する住宅営業手法をご用意しています。新人でも短期間で修得可能な「いい暮らし実現営業」、他社従来営業とは大きく差別化した“この家が欲しい”を引き出すコミュニケーションができる「気づき共感営業」、ハイエンド層のお客様に対応可能な「暮らし触発営業」などです。また、住宅事業を安定継続/発展するための、「商品」「商品開発」「集客・マーケティング」「営業」「設計」「マネージメント」の分野からアプローチする注文住宅事業の「総合ビルドアップサポート」やコンパクトな工務店様・住宅会社様の住宅事業をサポートする「お役立ちLabo」をご用意しています。
是非ご活用ください。
■住宅コンサルティング
https://www.housing-labo.com/consulting
■住宅営業/マネージメント/住宅設計研修
https://www.housing-labo.com/training
■お役立ちLabo
https://www.housing-labo.com/onlinesupport
《執筆者》
株式会社ハウジングラボ
営業企画課長 眞田 智子