お客様と住宅営業のコミュニケーションの取り方
2022/01/22

注文住宅営業において「お客様とのコミュニケーション」は「重要な営業スキル」ですが、現状は「会話」に頼ってしまっており、口から出る音声としての「言葉」への偏重傾向がみられます。
住宅営業分野に限って言えば、「営業が伝えたいことを伝えるという一方通行」になってしまい、双方向の会話にもなっていないというのも大きな問題点です。
注文住宅営業は、お客様との双方向のコミュニケーションによって住まいづくりを進めるビジネスです。
「お客様とのコミュニケーション」をどのように成立させていくのかについて考えてみましょう。
Contents
お客様と住宅営業のコミュニケーションの主体は視覚情報

視覚からの情報によるコミュニケーションは、様々な説がありますがコミュニケ―ション情報全体の80~90%以上を占めています。
耳からの情報は最大でも20%に満たないということになります。
SNSが一般化して、お客様がこんなインテリアにしたいと「SNSに上がった画像」をお見せになって、「いきなりインテリアの方向がこれまでの話と違ってしまった」ということをよくお聴きします。
「これまでのインテリアの話」は本当に共有化できていたのでしょうか。
体感体験という5感を使って互いにインテリア・イメージを共有化したのではない場合は、視覚的にインパクトのある画像がお客様のイメージをさらって行ってしまいます。
コミュニケーションは視覚情報をいかにうまく使うのかということになります。
お客様からの視覚情報をキャッチし、お客様に伝える際は視覚情報でお伝えするという原則を実戦に落と込んでこそ、お客様との双方向のコミュニケーションを成立させることができます。
お客様の表情から眼を離さない

コロナ禍にあってはマスクが常態化しています。
それでも目は見えていますので表情を読み取るには十分です。
「言葉は真意を表さない」ことはあっても「表情は真意を表す」のが常ですから、お客様の表情から眼を離さないというのはコミュニケーションの基本です。
簡単なようで結構難しい技術です。
モデル住宅をご案内する際は営業は当然バックオーライでお客様の表情から眼を離さないように先導します。
何かをご説明する際には、説明している最中もお客様の表情から眼を離さない。
特に説明終了後に、お客様の本音が表情に出ますので決して目を離さない。
接客中はあらゆる場面で意識をお客様の表情に集中して表情を読み取ります。
●本音は目の周辺の表情に出る
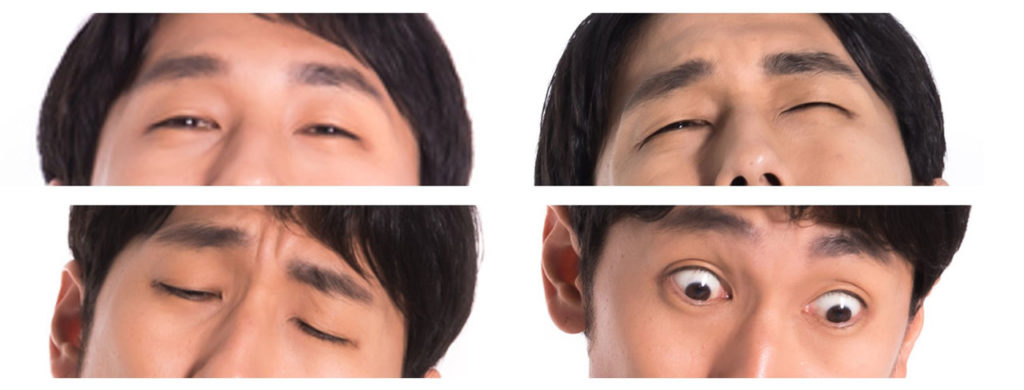
言葉では「YES」でも本音は全く異なるという場面は日常茶飯事です。
多くの営業の報告の矛盾はこのお客様からの情報の取り違いによるものです。
営業の心理として会社から「提案」したことへのお客様の「YES」という同意が欲しいと思っています。
その心理の裏付けの言葉が発せられると「お客様から同意を得た」と思い込みがちですが、その時の言葉のニュアンスは無視され、さらに、その時のお客様の表情は「見ていなかった」という内容の情報では、おそらく「同意」したと確信が持てるほどの情報確度がなくコミュニケ―ションが取れていないために起こる曖昧で矛盾を生じさせ、やがてお客様の信頼を失っていく典型的なコミュニケーション・エラーの現象です。
●お客様と住宅営業のコミュニケーションとは
住宅営業と住宅設計の間でよく使われる単語に「提案」という言葉がありますが、これは情報主導権が住宅の作り手側にあった時代の言葉です。
情報化社会ではお客様が望まれる情報は簡単にネットから入手でき、情報主導権はお客様にあると考えるべきです。
「提案」という言葉は「提案」へ誘導しようとする住宅営業側の意図があり、一歩間違えば失注に直結します。
一方通行の情報の押し付けはコミュニケーションではありません。
お客様からの情報提示はしっかりと受容れて理解し、こちらからは「住宅のプロとしての正しい情報提供」をして、お客様にご判断いただけるだけの材料をそろえて可能な限りビジュアルな情報として提示します。
判断されるのはお客様です。
【参考記事】
「お客様への提案営業は時代遅れ 多様化する価値観に対応する住宅営業方法」
「YES」でも「NO」でもよい。真意が知りたい
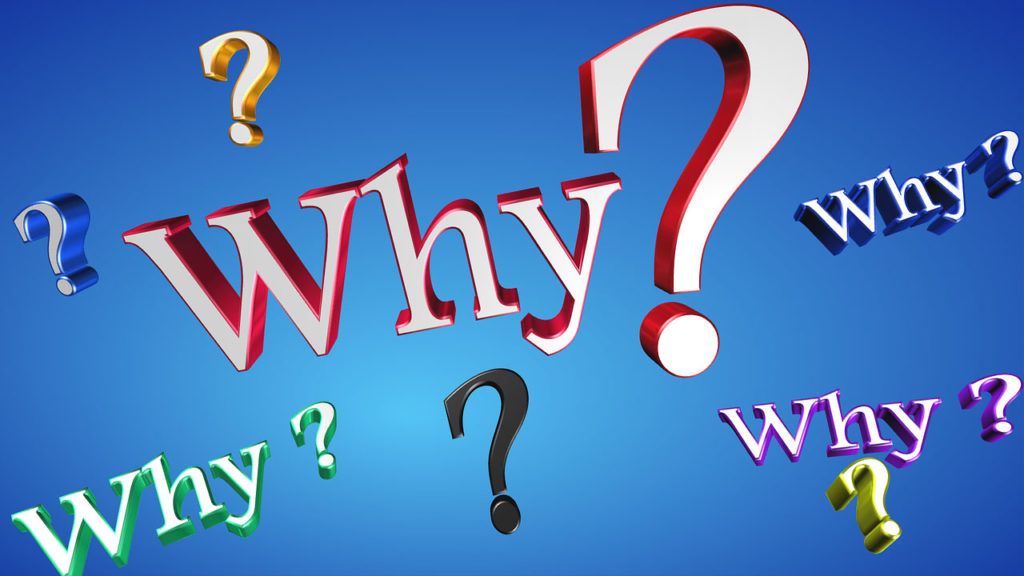
自社の商品特徴について「YES」でも「NO」でもよい、一番知りたいのは、そのようにお客様がご判断された真意、つまり原因です。
原因さえ掴めれば対策は絞られ方向性が見えてきます。
お客様が「NO」と言われていることを無理やりに「YES」と言わせることが住宅営業の仕事ではありません。
お客様がそうおっしゃった真因、原因を掴むためのコミュニケーションを丹念に積み重ねていくことが重要です。
「NO」と言われることは、その時点でのお客様の明確な意思表示があったということですから、その原因さえ掴めば対応策を打つことができます。
住宅営業のコミュニケーションとは、お客様の真意、意図をお客様と共有化することです。
●その場で結論を出さなくてもコミュニケーションは成立する
「『NO』とおっしゃる原因はそういうことなのですね。」まで持って来きたら、これでコミュニケーションは成立しています。
対策は次回に持ち越しても、その場のコミュニケーションは成立しています。
ここまでの経緯を整理して再確認し、次回の対策案を楽しみにして待っていただくようにします。
「住宅営業のコミュニケーションは双方向の情報のやり取りで合意できる結論を出す」ということですが、結論は出ていないが「問題点を共有化」するというところまでは進めたということを双方が確認すればコミュニケーションは成功です。
●コミュニケーションの合意はビジュアル資料で
「コミュニケーションの主体は視覚情報」です。
お客様と合意を図る場合は「パッと一目見たらわかる資料」でコミュニケ―ションを図るようにします。
視覚情報だけでは、コミュニケーション不足の場合、五感によるコミュニケーションとしてモデル住宅での体感体験などで納得を得るコミュニケーションをとります。
その際には特にお客様ご夫婦の表情から眼を離さないようにして、ご納得度を掌握するように心がけてください。
まとめ
住宅営業や住宅設計でのコミュニケーションは、言葉に頼らないという原則とコミュニケーションの中心はお客様です。
お客様から発せられるわずかに変化する微表情というコミュニケーション情報を敏感に受信することが出来るようになってください。
そのための第一歩はお客様の表情から眼を離さないということです。
デジタル化の社会で住宅営業の存在価値は「人と人とのコミュニケ―ション」にあります。
プライドを持って取り組んでいきましょう。
【参考】言葉に頼らない住宅営業手法「いい暮らし実現営業手法」
ハウジングラボでは、お客様の「納得」と「満足」を高めて標準6週間で受注を獲得する、スピード感のある住宅営業手法をご用意しています。
自社特徴の好印象化で「いいね」を積み重ねる住宅営業手法をもとに、住宅事業の安定経営をサポートします。
「商品」「商品開発」「集客・マーケティング」「営業」「設計」「マネージメント」の5分野からなる住宅営業サポートです。
是非ご活用ください。
■ハウジングラボの住宅営業サポート
https://www.housing-labo.com/consulting
住宅事業の安定継続/発展に役立つセミナーも開催しています。
■住宅営業セミナー
https://www.housing-labo.com/seminar
《執筆者》
株式会社ハウジングラボ
代表取締役社長 松尾俊朗
一級建築士











