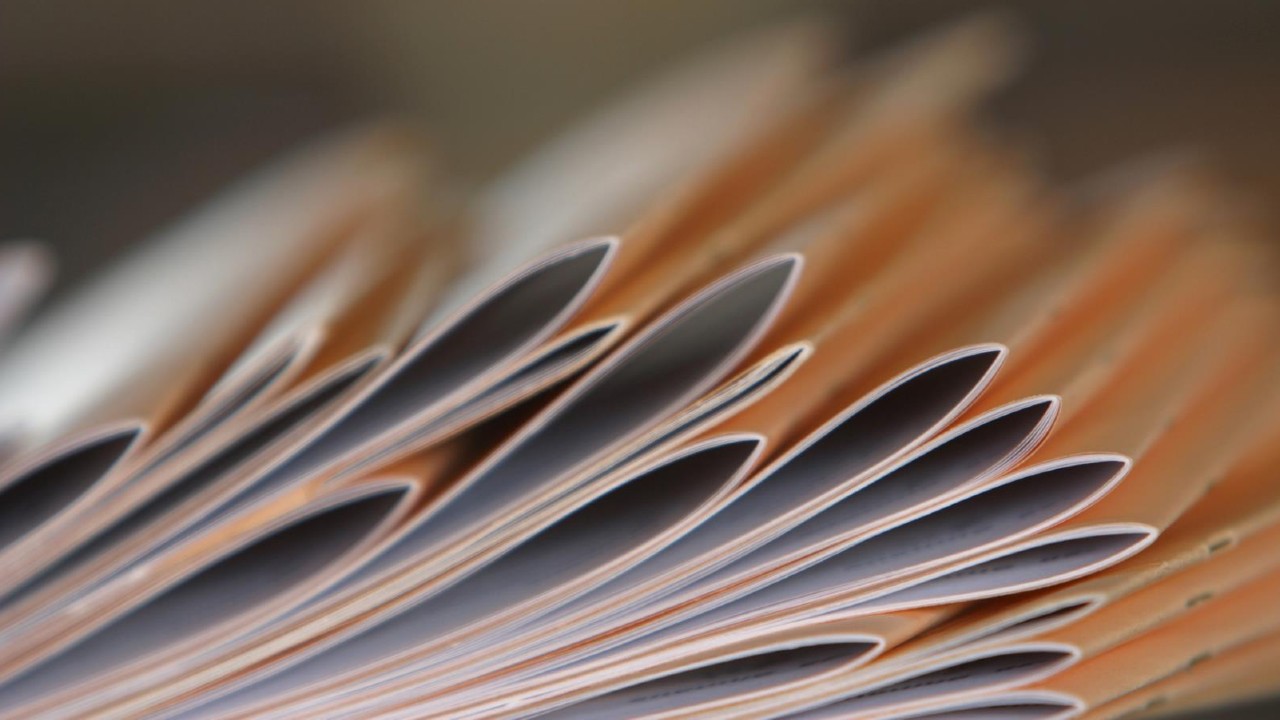住宅営業のご夫婦への対応のポイント
2022/08/26

ご主人様が主導し、奥様は夫の意思に沿う夫婦関係は、現在は減少傾向にあります。家族や夫婦関係の在り方や家事・育児などの行動も変化しており、ご夫婦関係を見極めずに、従来の「ご主人様が家庭内権力者」として対応していると、ご夫婦間に生じた住まいづくりへの考えに対する不協和音を見落としたりして、営業活動がうまく進まなかったりします。
今回は、夫婦関係の変化に合わせた住宅営業の対応方法について考えてみます。
「夫婦関係」が大きく変化
少子高齢化、晩婚化・晩産化、共働き世帯や未婚者の増加、コロナの影響など、夫婦関係や家族の姿が大きく変化しています。
若い世代の人が「夫、妻」と呼ぶ人と会ったことがあるのではないでしょうか。ある調査では、夫婦間での呼び方が「お父さん、お母さん」「おまえ、あなた」「おい、ねえ」などが減少し、お互いの名前やニックネームで呼び合うご夫婦が増加しています。また、奥様が家族以外の人にご主人様のことを話すときには、「主人」と呼ぶ人が減少しています。また、「友達夫婦」というお互いの生活や自由を尊重した関係の夫婦も増加しています。これは、お互いに対等な関係であり、「個人」を尊重するようになったと考えます。
【参考】リクルートブライダル総研
【参考】博報堂生活総合研究所
「力関係」の変化
家庭内での総合的な決定権という「力関係」にも大きな変化があります。奥様が住宅建築適齢期でもある30歳代以下のご夫婦の場合、若い世代ほど奥様に決定権があるという調査結果があります。
ご主人様に決定権 1988年 71.9% → 2018年 33.3%
奥様に決定権 1988年 9.5% → 2018年 36%
共働き世帯が増加し、奥様も働いてご自身が経済力を付けたことや働いている奥様のことも考慮して物事を決めたり進めたりしなければならない状況が背景にあり、奥様に決定権があるご家庭が増加したと考えます。
家庭のお金の管理者
それぞれのご家庭でのお金の管理は、家計管理が得意な方が管理する、共同口座で管理する、ご夫婦どちらかの収入を生活費・どちらかを貯金にするなど様々な方法がありますが、お金の管理に関する様々な調査結果を見ると、ご主人様が管理されているのは10%程度、奥様が管理されているのが40~70%、ご夫婦二人で管理されているのが40%程度で、お金の管理に関しては、ご主人様が管理されているケースは少数派という結果もあります。
ご夫婦への対応方法
上述したように、現在のご夫婦は、ご主人様・奥様と立場が対等もしくは奥様の方に決定権があったり、財布の紐を奥様が握っていたりする場合が多々あります。ご案内しながら、ご夫婦の関係がご主人主導・奥様主導なのかを見極め、対等もしくは奥様に「力」がある場合には、住宅営業活動を進める上で、ご主人様の方を尊重したり、奥様の方を尊重したりと偏った対応は避けるべきです。自社住宅をオンリーワンとして選んでいただくためには、どちらかの意見を重視するのではなくご夫婦両名の意見を尊重することをお勧めします。
ご夫婦両名からオンリーワンを獲得するコツ
まずは、ご主人・奥様それぞれの疑問点、不安点の解消を図ります。住宅営業が回答したことをご夫婦と共有して、本当にご安心されていることを確認することがポイントです。少しでも疑問や不安が残っていれば、パッと見てわかる資料でご説明して、ご安心いただくようにします。
そして、ご主人・様奥様のそれぞれの関心をお持ちのコトについて、住宅展示場や完成住まいの見学会などで体感体験していただきます。例えば、「広いリビングが欲しい」というご主人様には、ご夫婦やご家族みなさんに、普段通りの過ごし方を住宅展示場や完成住まいの見学会会場のリビングで再現していただき、会話する際に声が届きにくいなどのストレスがないかなど、体感体験を通して確認していただき、具体的なリビングの広さを決めていきます。「大きな収納スペースが欲しい」奥様には、そこに何を収納するのか、誰のものを収納するのか、実際に収納する人は誰かなど具体的に考えていただきながら、奥様だけでなくその収納スペースを使用する方すべてに、収納扉を開く、しまう、取り出す、を再現していただいて、その収納スペースに収納する際の手が届く最大の高さを共有するなど、体感体験を通して収納の使用目的や使用頻度に応じた設定を行うなど、一歩踏み込んだご案内をすることがポイントです。
まとめ
ご家庭内での決定権者がご主人様とは限らない現状では、ご夫婦関係を見極めたうえで対応することがポイントです。友達夫婦や奥様主導など、ご夫婦の関係が対等であったり奥様の方に主導権がある場合には、両名の意見を尊重し、関心をお持ちの部分で具体的な体感体験を通して実際の暮らしをイメージしていただきながら営業活動を進めることをお勧めします。
《執筆者》
株式会社ハウジングラボ
営業企画課長 眞田 智子